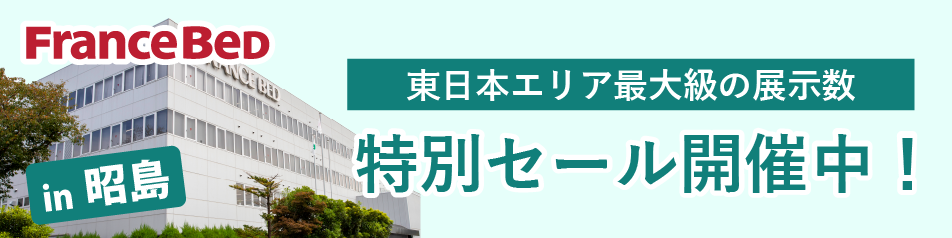.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
理想的な睡眠グラフとは?各睡眠段階のバランスと改善方法
公開日:2025.09.21(日)
スマートウォッチや睡眠トラッカーが身近になり、自分の睡眠グラフを毎朝チェックする人が増えています。深い睡眠やレム睡眠の時間がアプリに表示されても、「このグラフは理想的なのか?」「自分の眠りは良いのか悪いのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。
睡眠グラフには眠りの深さやサイクルが表示されていますが、理想的な睡眠グラフとはどのような形なのでしょうか。
この記事では、ノンレム睡眠とレム睡眠の正常なリズムや各段階の理想的な割合を分かりやすく説明します。また、自分のグラフとの違いを読み解くポイントや、理想から外れた部分を改善するための具体的な方法もご紹介します。
毎晩のデータを活用して「より良い眠り」を実現し、朝の目覚めをスッキリと感じられるよう一緒に取り組んでみましょう。
睡眠グラフで見る理想の睡眠パターン
ノンレム睡眠とレム睡眠:それぞれの役割
人間の睡眠は大きく分けてノンレム睡眠(深い眠り)とレム睡眠(浅い眠り)の2種類が交互に現れます。
ノンレム睡眠では、脳の活動が抑えられ、身体も深く休息します。この時間に成長ホルモンが分泌され、疲労回復や細胞の修復が行われます。つまり、身体のメンテナンスに重要な時間です。
一方、レム睡眠では、筋肉は弛緩して体は休んでいますが、脳は活発に動いています。日中に蓄積された情報や記憶の整理・定着が行われ、感情のリセットにも関わっています。夢を見るのも主にこの時間帯です。
ポイント:
- ノンレム睡眠=「脳も休む深い眠り」(身体の疲労回復・組織修復)
- レム睡眠=「脳が動く浅い眠り」(記憶整理・感情処理)
90分周期の睡眠サイクルとは
私たちの睡眠は、ノンレム睡眠とレム睡眠が約90分ごとに1セットとなって繰り返される睡眠サイクルを形成しています。
健康な成人の場合、眠り始めてから最初の30〜60分ほどで最も深いノンレム睡眠に入ります。その後眠りが浅くなって約10〜20分間のレム睡眠へ移行し、これを一晩で4〜5回程度繰り返すのが正常なパターンです。
睡眠全体に占める理想的な比率は「ノンレム約80%:レム約20%」とされています。
実際の睡眠では、夜の前半ほど深いノンレム睡眠が多く、朝方に近づくにつれてレム睡眠の割合が増えていくのが正常なリズムです。明け方頃のレム睡眠が終わるタイミングで起きることができると、非常に爽快な目覚めを得られます。
理想的な睡眠とは、適切な長さの睡眠時間(一般に7〜8時間程度)を確保しつつ、この90分周期のリズムが崩れずに維持されている状態です。
各睡眠段階の理想的な割合
深い睡眠・浅い睡眠・レム睡眠のバランス
一晩の睡眠における各睡眠段階の理想的な割合は、健康な成人の場合は以下のようなバランスが目安となります:
- 深い睡眠(徐波睡眠):約15〜20%(全睡眠時間の約1〜2割)
- 浅い睡眠(ノンレム睡眠第1・2段階):約50〜60%(全体の半分前後)
- レム睡眠:約20〜25%(全睡眠時間の約1/5程度)
- 覚醒(中途覚醒の時間):できるだけ5%未満
例えば7時間眠った場合、深い睡眠は合計で約1〜1.5時間、レム睡眠は合計で約1.5時間程度、残りの4時間前後が浅い睡眠というイメージです。
深い睡眠は主に就寝直後の数時間に集中し、レム睡眠は明け方近くになるほど長くなります。そのため「入眠直後でしっかり深い眠りに入り、後半はスムーズにレム睡眠へ移行していく」という時間の流れも重要なポイントです。
ただし、上記の割合はあくまで目安であり個人差も大きい点に注意しましょう。体質や年齢、その日の体調によって幅があります。重要なのは自分自身が日々よく眠れたと感じられるかという主観的な満足感です。
一晩ごとの数値に神経質になりすぎず、数週間〜数ヶ月単位で見た自分の睡眠傾向を把握し、無理のない範囲で改善を図っていくことが大切です。
理想と違う場合の原因と対処法
自分の睡眠グラフを理想パターンと見比べたとき、気になる部分があることもあるでしょう。それぞれのケースについて、考えられる原因と改善方法を見ていきます。
深い睡眠が少ない場合
深い睡眠の割合が10%前後と著しく低い場合、肉体的な疲労回復が不十分になりやすく、朝起きたときに熟睡感が得られにくくなります。
考えられる原因:
総睡眠時間の不足 深い睡眠は主に睡眠前半に集中するため、そもそもの睡眠時間が短すぎると絶対量が減ってしまいます。まずは6時間以上、できれば7時間以上の継続した睡眠時間を確保することが重要です。
就寝前の脳の過活動 寝る直前まで仕事や考え事をしていたり、強いストレスを抱えた状態だと、交感神経が優位なまま眠りにつくことになり深い眠りに移行しにくくなります。在宅勤務などでオン・オフの切り替えが曖昧になった影響で、「眠りが浅くなった」と感じる人も増えています。
生活リズムの乱れ 就寝時刻や起床時刻が日によって極端にズレる生活をしていると、体内時計のリズムが乱れて睡眠の深さにも影響します。平日と休日で寝る時間が大きく違う場合は要注意です。
アルコール・カフェインの摂取 就寝前のカフェイン摂取は脳を覚醒させ、深い眠りへの移行を阻害します。就床前の4時間以内はカフェインを控えることが大切です。また、寝酒は一時的に寝つきを良くしますが、後半の睡眠を浅くし中途覚醒を増やしてしまいます。
改善策:
深い睡眠を増やすには、まず十分な睡眠時間を毎日確保し、就寝前は意識的にリラックスする時間を設けましょう。
寝る1〜2時間前から部屋の照明を暖色の薄暗い明かりに変えるのは効果的です。オレンジ色の穏やかな照明は脳の興奮を鎮め、自然な眠気を促してくれます。
スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトも脳を刺激するため、就床前にはゲームやSNS閲覧を避けましょう。代わりに本を読む・ストレッチをする・ぬるめの入浴をするなど、心身を落ち着ける習慣に切り替えてみてください。
寝室の環境も見直してみましょう。室温や湿度は快適と感じる範囲に調節し、照明も真っ暗が不安でなければ豆電球程度の明かりに留めるなど、スムーズに深い眠りに入れる環境づくりを意識します。
レム睡眠の割合が極端な場合
レム睡眠の割合が極端に多い場合、相対的にノンレム睡眠(特に深い睡眠)が不足している可能性があります。レム睡眠は通常、全体の20%程度に収まるものですが、明らかに3割以上など高すぎる場合は以下のような原因が考えられます。
ストレス・不安の影響 精神的ストレスが強いと睡眠中も交感神経が高ぶりがちで、深い眠りに入りづらくなります。その結果、浅い眠りやレム睡眠の比率が高まる傾向があります。
寝室の環境刺激 寝室が明るすぎたり物音がうるさかったりすると眠りが浅く頻繁に目が覚めるため、レム睡眠や覚醒状態が増えてしまいます。特に光はレム睡眠を誘発しやすい刺激です。
入浴のタイミング・体温 就寝前の熱すぎるお風呂も深部体温を上げすぎてしまい、深い睡眠の立ち上がりを妨げます。理想的には就寝90分ほど前までに40℃前後のぬるめの湯に浸かり、体温がスムーズに下降する流れを作ると良いでしょう。
一方で、レム睡眠が極端に少ない場合(毎晩レム睡眠が全体の10%未満など)も考えられます。要因としてはまず睡眠時間の不足が挙げられます。レム睡眠は睡眠後半に多く出現するため、総時間が短いと比例して減ってしまうのです。
改善策:
レム睡眠の異常を感じる場合も基本的には原因への対処が先決です。ストレスが原因ならリラックス法の導入(就寝前の深呼吸・軽いストレッチなど)、環境要因なら遮光・防音対策、生活習慣では適度な運動や朝の太陽光を浴びる習慣で体内時計を整えることが有効です。
重要なのは日中に支障を感じるほどの不調があるかどうかです。強い眠気や疲労感が残る場合には専門医に相談することも検討しましょう。
途中で何度も目覚めてしまう場合(中途覚醒)
睡眠グラフ上で細切れに覚醒の記録が残っている場合、中途覚醒が頻繁に発生していることを意味します。正常な睡眠でも一晩に数回は短い覚醒がありますが、10分以上起きてしまうような覚醒が毎晩のようにある場合、睡眠の質への影響が大きくなります。
考えられる原因:
睡眠環境の問題 夜間に物音や光によって目が覚めてしまうケースです。近所の車やバイクの音、ペットや同居の家族の物音、暑さ・寒さなどが該当します。
生活習慣の問題 就寝前に大量の水分を取って夜中にトイレに起きてしまう、夕食が遅く胃もたれで目が覚める、アルコールの分解で夜中に眠りが浅くなる、といった生活習慣由来の覚醒もあります。
いびき・無呼吸などの睡眠障害 大きないびきを伴う睡眠時無呼吸症候群では、一晩に何十回と短い覚醒が起こります。その結果グラフが極端に分断されたり、深い睡眠が著しく減少したりします。
改善策:
環境や生活習慣の要因であれば、原因を取り除くことで中途覚醒はかなり減らせます。環境面では「暗く静かな寝室」を徹底し、生活面では「規則正しい睡眠習慣」と「刺激物を避ける」ことが基本です。
短い覚醒自体は誰にでも起こるものなので、神経質になりすぎないことも大切です。一度目が覚めてしまっても、「また寝付けるだろう」とリラックスして過ごしてください。
長引く不眠や明らかな睡眠障害の症状がある場合には、遠慮せず睡眠専門のクリニックに相談することで適切な治療やアドバイスが得られます。
快眠のためのポイントと寝具環境の見直し
理想の睡眠グラフに近づけるためには、生活習慣と睡眠環境(寝具など)の両面からアプローチすることが有効です。今日から実践できる快眠のポイントと、特に重要な「寝具選び」について詳しく解説します。
良い睡眠を得るための生活習慣チェックリスト
睡眠時間の確保 個人差はありますが、成人では最低6時間、できれば7〜8時間程度の睡眠時間を毎日確保しましょう。眠る時間帯もできるだけ一定に保ち、平日と休日で極端な寝だめ・夜更かしをしないことが理想です。
就寝前のリラックス 寝る前は強い光や興奮する作業を避け、心身をリラックスさせます。照明は暖色で薄暗くし、スマホやパソコンは寝る直前には見ない習慣をつけましょう。軽いストレッチや読書、ぬるめの入浴など自分なりのリラックス法を見つけてください。
食事・飲み物の工夫 就寝前のカフェイン(コーヒー、緑茶、エナジードリンク等)は控えます。夕食は寝る3時間前までに済ませ、アルコールは適量を守って深酒しないようにします。
適度な運動習慣 日中に軽く体を動かすことは夜の睡眠を深める助けになります。激しい運動はかえって寝つきを悪くする場合もあるので、ジョギングやヨガなど無理のない範囲で継続することが大切です。朝起きたら日光を浴びる習慣も体内時計を整える効果があります。
ストレスケア ストレスが睡眠の大敵であることを忘れず、自分なりのストレス発散法を持ちましょう。誰かに話を聞いてもらう、日記を書いて気持ちを整理する、アロマや音楽で癒される時間を作るなど、心の緊張をほぐす工夫が質の良い睡眠につながります。
質の良い睡眠のための寝具選び:マットレスの重要性
最後に、睡眠環境の要である寝具(特にマットレス)について触れておきます。どんなに生活習慣に気を配っても、寝具が体に合っていなければ快眠は得られません。
マットレスが硬すぎたり柔らかすぎたりすると寝姿勢が不自然になり、夜中に何度も寝返りを打って深い眠りが途切れてしまうことがあります。逆に、自分に合ったマットレスでしっかり体圧を分散できれば余計な寝返りや覚醒が減り、深い睡眠が長く持続することが期待できます。
実際、日本の寝具メーカーである西川が行った検証でも、特殊構造のマットレスを使用することで最も深いノンレム睡眠の持続時間が延び、睡眠の質が向上したという結果が報告されています。
では、具体的にどんなマットレスを選べば良いのでしょうか?
ポイントは、自分の体格・睡眠姿勢に合った適度な反発力と支持力を持つマットレスを選ぶことです。横になったときに腰や肩に過度な負担がかからず、背骨が自然なS字カーブを保てる寝姿勢を維持できるものが理想です。
例えば、ポケットコイル式のマットレスは体のラインを点で支えフィット感が高く、同時に隣の人の動きが伝わりにくい特徴があります。高反発ウレタンや特殊フォームを用いたマットレスは身体を面で支えてくれるため、沈み込みすぎず自然な寝返りをサポートしてくれます。
亀屋家具では、世界的に評価の高いシモンズ、シーリー、サータなどの一流ブランドから、国内老舗の日本ベッド、フランスベッドといったメーカーに至るまで、多彩なブランドのマットレスを取り扱っています。
それぞれのブランドが快眠のために独自の技術と品質を追求しており、例えばシモンズは体圧分散に優れたポケットコイルの先駆者、シーリーやサータは医療分野の知見を活かした設計で理想的な寝姿勢を保つマットレスを提供しています。昭和西川の「ムアツ布団」のように高反発素材で寝返りを促し血行を妨げないコンセプトの寝具も人気です。
ぜひ専門スタッフのアドバイスを受けながら、ご自身の身体に最適な一枚を選んでみてください。マットレスを新調したその日から「睡眠グラフが改善した」「朝の目覚めが良くなった」というお客様の声も多く、寝具の見直しは理想の睡眠に近づく近道と言えるでしょう。
まとめ:理想のグラフは快眠への指標
一晩の睡眠グラフには、私たちの眠りの質とリズムがはっきりと表れます。理想的な睡眠グラフは「90分周期のリズムが整い、深い睡眠とレム睡眠のバランスが適正な形」ですが、多少のズレは誰にでもあるものです。
大切なのはグラフの傾向から自分の睡眠状態を知り、改善に活かすことです。毎日のデータを通じて「昨夜はいつもより深い睡眠が少なかったな、今日は早めに寝よう」「運動した日はレム睡眠が適度に増えている」といった気付きが得られるでしょう。
睡眠は人生の約3分の1を占める大切な時間です。睡眠グラフという客観データと、朝の目覚めや日中の調子といった主観的な実感の両方に耳を傾けながら、理想のパターンに近づけるよう少しずつ取り組んでみてください。
生活習慣の改善や寝具の見直しによってグラフがゆるやかに理想形へと近づき、何より「ぐっすり眠れた!」という実感が得られるようになれば、きっと毎日の活力も違ってくるはずです。データを味方につけて、快適な眠りと爽やかな目覚めを手に入れましょう。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。