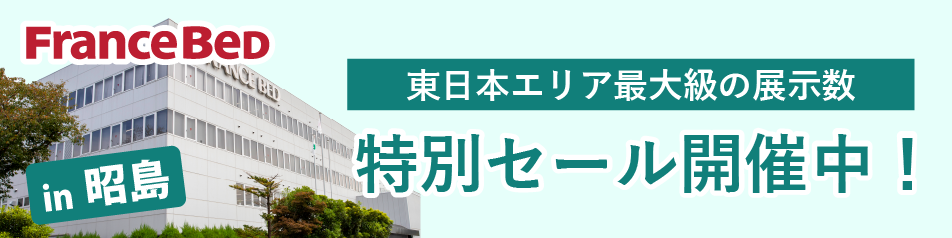.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
睡眠の悩みは何科で受診?症状別の病院選びと治療内容を解説
公開日:2025.08.23(Sat)
夜なかなか眠れない、昼間に強い眠気が続く...こんな睡眠の悩みはありませんか?
生活習慣を見直しても改善されない場合は、専門の医療機関で相談することをおすすめします。しかし「睡眠の問題はどこの病院に行けばいいの?」と迷う方も多いでしょう。
この記事では、不眠症や睡眠時無呼吸症候群など症状別に受診すべき病院の選び方や、病院の睡眠外来で受けられる検査・治療内容をわかりやすく解説します。
眠れない毎日を我慢せず、適切な医療の力で解決への一歩を踏み出しましょう。
睡眠障害は早めの受診を―5人に1人が抱える身近な問題
現代社会では日本人の約5人に1人が睡眠に関する悩みを抱えていると言われています。
睡眠の問題は、日中のパフォーマンス低下を招くだけではありません。うつ病や生活習慣病(高血圧・糖尿病など)とも深い関係があります。十分に眠れない状態が続けば、心身の健康を損ない、仕事や家事でのミス、重大な事故につながる恐れもあります。
しかし日本では、睡眠トラブルに悩んでも病院に相談する人の割合は諸外国より低いことが分かっています。実際に20人に1人が睡眠薬を服用している一方で、不眠に悩んでも医療機関を受診せず、アルコールなどに頼るケースも見られます。
このような自己流の対処には限界があり、副作用や依存のリスクも伴います。
症状が長引く場合は早めに専門医へ
重要なのは、症状が長引く場合は早めに専門医に相談することです。
厚生労働省が公表した最新の睡眠指針(案)でも、生活習慣の改善を試みても睡眠の問題が続き、日中生活に支障が出る場合は「速やかに医師に相談しましょう」と強調されています。
慢性的な不眠や過度の眠気は、れっきとした"睡眠障害"です。適切な診断と治療によって改善が期待できます。気になる症状を抱えているなら、我慢せず専門家の力を借りましょう。
症状別:睡眠の悩みに対応する診療科の選び方
「どの診療科に行けばいいのか分からない」という戸惑いはもっともです。
実は現在、日本の病院では「睡眠科」という診療科名は標榜(看板に表示)できません。睡眠障害に対応する医師は、内科・精神科・耳鼻咽喉科など他の専門科で研鑽を積んだ上で睡眠医療の知識を身につけているのが一般的です。
一部の大学病院では「睡眠医療センター」や「睡眠外来」の名称で専門外来を設置していますが、数はまだ多くありません。
近い将来「睡眠障害科」が誕生する可能性も
近年、日本睡眠学会が診療科名に「睡眠障害」を追加するよう厚労省に要望し始めており、睡眠専門クリニックのニーズが高まっています。
医師からも「まず精神科というのは患者さんにとって受診のハードルが高い」ため、睡眠専門の受け皿が増えることを期待する声が上がっています。
症状別・受診先の目安
では、具体的にどの症状のとき何科を受診すればよいのでしょうか?
下記に主な症状別の対応科目をまとめました。迷った場合は、まず近くの内科で相談し、必要に応じて適切な専門医を紹介してもらう方法もあります。
また、お住まいの地域に睡眠専門医(日本睡眠学会認定医)のいる医療機関があれば、そちらを受診するのも良い選択です。
〈症状別・受診先の目安〉
- 夜眠れない(不眠症状):心療内科・精神科(ストレスや精神面の影響を考慮)。迷う場合はまず内科でも相談可能
- いびき・無呼吸がある(睡眠時無呼吸症候群疑い):内科(特に呼吸器内科・循環器内科)または耳鼻咽喉科。気道の構造的な問題が疑われる場合は耳鼻科で検査
- 日中の強い眠気(居眠りが繰り返される):脳神経内科または精神科。ナルコレプシー等の過眠症を念頭に専門的検査が可能な科へ
- 睡眠リズムが乱れている(夜型・昼夜逆転など):精神科・心療内科。生活リズムの障害が疑われる場合は体内時計の調整治療を実施
- 子どもの睡眠問題(夜更かし・朝起きられない等):小児科。15歳以上で不登校を伴うようなケースでは児童精神科の受診も検討
- その他の特殊な症状:睡眠中の異常行動(大声で叫ぶ・暴れる等のレム睡眠行動障害)や手足のムズムズ感(むずむず脚症候群)は脳神経内科が適しています。睡眠中のひどい歯ぎしりは歯科でマウスピース作製など相談できます
不眠の悩み:何科を受診すべき?
夜なかなか寝付けない、眠りが浅く途中で何度も目が覚める、といった不眠症状に悩む場合は、まず心療内科や精神科への受診を検討しましょう。
ストレスやうつ病、不安障害などこころの問題が不眠の引き金になっているケースが少なくないためです。実際、不眠患者のかなりの割合で精神疾患の併発が報告されています。
内科での相談も可能
専門の睡眠外来が近くになければ、内科で相談する方法もあります。内科医が睡眠障害に詳しければ対応してもらえますし、必要なら適切な専門医への紹介を受けることも可能です。
いずれにせよ、「眠れない」ことを遠慮なく医師に伝え、生活習慣や心理面も含めたアプローチを受けることが早期改善への近道です。
いびき・睡眠時無呼吸:何科を受診すべき?
大きないびきや寝ている間に呼吸が止まると指摘された場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。
まずは内科を受診し、必要に応じて呼吸器内科や循環器内科といった専門分野の医師に相談すると良いでしょう。
放置すると危険な合併症のリスク
睡眠時無呼吸は、肥満や鼻詰まりなど様々な要因で気道が狭くなることで生じます。
放置すれば日中の強い眠気による事故リスクや、高血圧・心疾患・脳卒中など合併症につながることもあります。
耳鼻咽喉科での詳しい検査も重要
原因を詳しく調べるには、鼻や喉の構造チェックや画像診断が必要になるため、耳鼻咽喉科で詳しく検査することも勧められます。
例えば鼻中隔のゆがみや扁桃肥大が見つかれば、外科的治療で症状が改善するケースもあります。
日中の強い眠気:何科を受診すべき?
十分眠っているはずなのに日中に耐え難い眠気に襲われる場合、過眠症(ナルコレプシーや特発性過眠症など)の疑いがあります。
思春期~青年期に発症しやすいこれらの病気では、授業中や仕事中に居眠りしてしまい生活に支障が出ます。このような症状があるときは、脳神経内科や精神科を受診しましょう。
詳細な検査が可能な専門医を探そう
過眠症の診断には、一晩入院して行う終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)と、翌日の反復睡眠潜時試験(MSLT)による詳細な検査が必要です。
これらは限られた施設でしか実施できないため、日本睡眠学会専門医がいる病院や、睡眠障害の専門外来を探すことをおすすめします。
高齢者で日中の眠気が強い場合は、認知症との区別も必要になるため、まずは専門医に相談して適切な検査を受けてください。
睡眠リズムの乱れ:何科を受診すべき?
夜更かしが続いて朝起きられなくなる、あるいは夕方から極端に眠くなって夜中に目が覚めてしまう――このような概日リズム睡眠障害(体内時計の不調)の疑いがある場合は、精神科や心療内科を受診しましょう。
専門的な治療で体内時計を調整
専門医のもとでは、高照度光療法(朝に強い光を浴びる治療)やメラトニン作動薬の処方によって、乱れた睡眠周期の調整を行います。
本人の意思で早寝早起きをしようとしても矯正が難しいケースでも、適切な治療によって社会生活リズムを整えられる可能性があります。
また背景にうつ病や発達障害などが隠れていないか評価し、それらへの対応が並行して行われることもあります。
子どもの睡眠問題:何科を受診すべき?
小児の夜間睡眠の悩み(夜驚症・夜尿症など)や、朝起きられない・日中に居眠りしてしまうといった問題は、基本的に小児科が窓口になります。
中学生〜高校生くらいで「朝起こしても起きられず学校に行けない」という場合、単なる生活リズムの乱れ以外に起立性調節障害や精神的要因が関わっていることもあります。
専門的なサポートを早めに
このようなケースでは、小児科と連携している児童精神科や思春期外来が適切な治療につなげてくれるでしょう。
「子どもだからそのうち治る」と放置せず、保護者の方は早めに専門医に相談してみてください。
なお、小児の睡眠障害に関しては専門施設が限られるため、必要に応じて大規模病院の睡眠外来(小児睡眠障害外来など)を紹介してもらう方法もあります。
その他の睡眠トラブル:何科を受診すべき?
上記以外にも、睡眠中の様々な異常現象があります。
レム睡眠行動障害
睡眠中に突然大声で叫ぶ・暴れるといった行動が見られる場合、レム睡眠行動障害が疑われます。これは高齢者に多く、将来的にパーキンソン病など神経変性疾患の前兆となることもあるため、脳神経内科での診察をおすすめします。
確定診断には一晩の睡眠検査で脳波や筋電図を詳しく調べる必要があります。
むずむず脚症候群
夜寝床に入ると脚がむずむずして眠れないという場合はむずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)かもしれません。
脳内の鉄分やドーパミン神経の問題が背景にあるとされ、これは脳神経内科が担当する病気です。適切な薬物療法で症状改善が期待できます。
歯ぎしり
睡眠中の歯ぎしりがひどい場合は歯科でマウスピース治療の相談ができます。
いずれの場合も、「こんな症状は変かも?」と思ったら一人で抱え込まず専門医に問い合わせてみましょう。
睡眠外来で行われる検査と主な治療方法
睡眠外来で受けられる主な検査
睡眠障害専門の外来では、まず医師による問診・診察が丁寧に行われます。
いつからどのような症状があり、生活習慣や既往症、就寝前の行動(カフェイン摂取やスマホ使用など)について詳しく質問されるでしょう。必要に応じて睡眠日誌(睡眠ログ)の記録をお願いされることもあります。
客観的な評価が必要な場合、以下のような検査が実施されます。
簡易睡眠検査
自宅でできる簡易検査機器を用い、一晩のいびき音や血中酸素飽和度を測定します。
主に睡眠時無呼吸症候群のスクリーニングに使われ、入院不要で手軽です。保険適用時の自己負担は数千円程度と比較的安価です。
終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)
病院や検査施設に一泊し、脳波・眼球運動・心電図・筋電図・呼吸・血中酸素など全身の生体活動を一晩かけて記録する精密検査です。
不眠症や睡眠時無呼吸、周期性四肢運動障害、レム睡眠行動障害など様々な睡眠障害の確定診断に用いられます。
検査当日は全身に電極やセンサーを装着して就寝し、睡眠の深さや異常な動きを詳細に解析します。保険適用の場合、自己負担額は医療機関にもよりますが1泊2日で約2万~5万円前後(3割負担の場合)が目安です。
反復睡眠潜時試験(MSLT)
主にナルコレプシーなど過眠症の診断のために行われる検査です。
夜間のPSG検査を実施した翌日に、日中の一定間隔で数回の短い睡眠機会を与え、入眠までの時間や睡眠の状態を測定します。
日中に異常に速やかに眠りに落ちレム睡眠に入ってしまう傾向を確認できれば、ナルコレプシーの有力な根拠となります。MSLTは専門医療機関でのみ実施され、PSGと合わせて半日〜1日追加の検査時間が必要です。
その他の検査
むずむず脚症候群が疑われる場合には鉄欠乏の有無を調べる血液検査、睡眠中のてんかん発作が疑わしい場合には脳波検査など、症状に応じた検査が行われます。
いずれの検査も医師と相談の上で進められ、不要な検査が行われる心配はありません。
睡眠障害に対する主な治療法
診断結果に応じて、患者さん一人ひとりに適した治療が提案されます。
治療の柱となるのは大きく非薬物療法(生活指導や機器を用いる療法)と薬物療法です。
生活習慣の改善指導
不眠症の基本治療として、睡眠衛生指導すなわち生活習慣の改善が重視されます。
具体的には、「毎朝決まった時刻に起床して朝日を浴びる」「就寝前の1〜2時間はスマホや強い光を避ける」「眠くない時は無理に布団に入らない」等のアドバイスが行われます。
日中の適度な運動や就寝前のリラックス法、静かで快適な寝室環境(照明・室温・寝具など)の整備も助言されます。例えば寝室の温度や湿度を適切に保ち、体に合ったマットレスや枕を使うことは睡眠の質向上に有効です。
これら睡眠衛生の工夫だけでも不眠が解消する場合もあり、治療の第一歩となります。
認知行動療法(CBT-I)
不眠症には薬に頼らないアプローチとして認知行動療法も有効です。
睡眠専門の臨床心理士や精神科医によるカウンセリングを通じて、「眠れないことへの過度の不安」を和らげ、悪循環を断つ方法を学びます。
例えば、寝つけなくても焦らず一旦ベッドを出てリラックスする習慣づけ(刺激制御療法)や、あえて睡眠時間を制限して睡眠効率を上げる方法などを段階的に実践します。
CBT-Iは即効性こそありませんが、不眠の根本改善につながり、薬の減量・中止も期待できる有望な治療です。国内でも対応できる医療機関が増えてきており、オンラインアプリによる認知行動療法プログラムが開発されている例もあります。
持続陽圧呼吸療法(CPAP)
睡眠時無呼吸症候群と診断された場合、中等症以上ではCPAP療法が標準治療となります。
就寝時に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道が塞がらないよう圧力をかけ続ける装置です。CPAPにより無呼吸や低呼吸が劇的に改善し、日中の眠気や合併症リスクを大幅に減らせます。
ただし機器を毎晩使用する必要があり、慣れるまでに時間がかかる場合もあります。治療開始時は専門スタッフが装着方法やお手入れ方法を丁寧に指導してくれるので安心です。
CPAP装置は通常購入ではなくレンタルで提供され、健康保険が適用されます。その自己負担費用は月額約5,000円程度(3割負担の場合)で、定期的な診察費も含めてこの程度です。
軽症の無呼吸症候群でCPAP適用とならない場合や、マスクにどうしても適応できない場合には、歯科でのマウスピース(スリープスプリント)作製や、耳鼻科での外科的治療(扁桃摘出や鼻中隔矯正など)も選択肢となります。
薬物療法
不眠症や概日リズム障害、むずむず脚症候群など、それぞれの症状に応じて適切な薬の処方が行われます。
不眠症の治療薬
不眠症に対しては、現在ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬が一般的に用いられます。これらは即効性がありますが、長期連用による依存や認知機能への影響に注意が必要なため、医師の指示のもと最小限の量で用います。
一方、寝つきは悪くないのに夜中に何度も目覚めてしまうタイプの不眠には、持続時間の長い睡眠薬や、場合によっては抗うつ薬・抗不安薬が処方されることもあります。
その他の睡眠障害の治療薬
概日リズムのずれにはメラトニン受容体作動薬(ラメルテオンなど)が有効で、体内時計を徐々に前進・後退させる目的で使われます。
むずむず脚症候群には、脳内のドーパミン神経に作用する薬(プラミペキソール等)や鉄剤補充が行われます。
またナルコレプシーなどの過眠症には、日中の眠気を抑える中枢神経刺激薬や精神刺激薬(モダフィニルなど)が処方されます。
適切な薬物療法を受けるために
いずれの薬物療法も、症状と安全性を見極めながら最適な薬剤・用量を選ぶのが専門医の役割です。
「睡眠薬=怖いもの」というイメージがあるかもしれませんが、医師の管理のもと正しく使えば症状改善に大きく役立ちます。必要な期間だけ薬に助けてもらいながら、根本的な生活改善や別の治療と組み合わせていくことが望ましいでしょう。
検査・治療にかかる費用の目安
睡眠に関する診療は健康保険が適用されるケースが多いため、費用面のハードルはそれほど高くありません。
自己負担額(3割負担の場合)の目安をまとめます。
診察費
初診料は病院規模によりますが数千円程度です。専門外来の場合、時間をかけて問診するため若干高くなることもありますが、通常の保険診療範囲です。再診料は1回数百円~千円台です。
検査費
上述した簡易検査は自己負担で数百円~数千円程度、終夜PSG検査は入院費込みで約1~5万円程度が目安です。
例えば国立精神・神経医療研究センター病院では1泊2日のPSG検査入院で自己負担約5万5千円と案内されています。検査内容や医療機関によって費用に幅がありますので、事前に確認すると安心です。
治療費
CPAP療法はレンタル料と定期管理料を合わせて月額5千円前後(3割負担)です。
マウスピース治療は歯科で保険適用の場合、片顎で1~2万円程度と言われます。睡眠薬など薬代は処方される薬剤によりますが、ジェネリック医薬品を使えば1か月千円前後に収まることも多いです。
認知行動療法は保険適用下で行われる場合、数回のセッションで数千円~1万円台程度でしょう。
費用の心配は不要
症状や保険の負担割合によって実際の費用は変動しますが、「睡眠外来は高額なのでは?」と心配しすぎる必要はありません。
不安な場合は受診前に病院の窓口に問い合わせ、検査や治療の概算費用を教えてもらうこともできます。睡眠障害は適切な診断と治療を受ければ医療保険の範囲内で十分ケア可能な病気です。
まとめ:眠りの悩みは一人で抱え込まず専門医に相談を
質の良い睡眠は、心身の健康と生活の質を支える重要な土台です。
「眠れない」「日中に眠くて仕方がない」という状態が続くのは、決して特殊なことではなく多くの人が経験しうる身近な問題です。しかし、それが毎日の生活に支障を来すようであれば早めに医療機関を受診することが大切です。
この記事で解説したように、睡眠の悩みには原因や症状に応じて適切な診療科があります。各分野の専門医が協力し合って診療に当たる体制も整いつつあります。
つらい症状を無理に我慢する必要はありません。睡眠障害は治療可能であり、改善すれば日中の充実した生活を取り戻すことができます。
睡眠薬に頼ることに不安を感じる方もいるかもしれませんが、医師と十分に相談しながら進めれば心配はいりません。
ぜひ信頼できる医療の力を借りて、快眠への第一歩を踏み出してください。睡眠の悩みから解放され、翌朝すっきり目覚められる日常を取り戻しましょう。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。