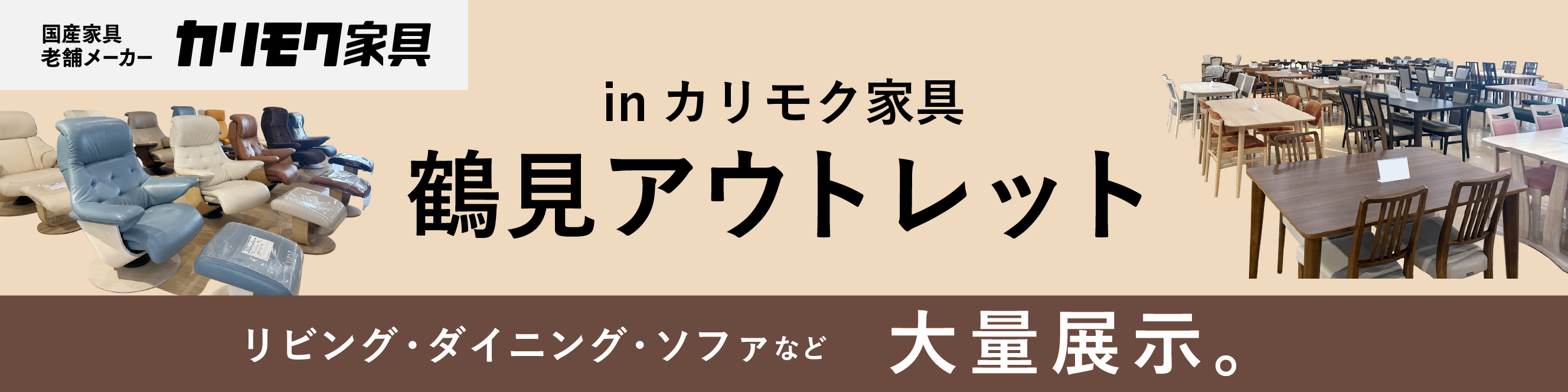.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
睡眠に効果的な音楽BGMとは?リラックスできるおすすめ曲と聴き方
公開日:2025.07.05(Sat)
布団に入ってもなかなか寝付けない――そんな経験はありませんか?実は、心地よい音楽BGMを使うことで、リラックスして眠りに入りやすくなるかもしれません。この記事では、睡眠に効果的な音楽の科学的な根拠や、おすすめのヒーリング音楽・自然音BGM、さらに安全な聴き方のポイントをご紹介します。音楽の力を借りて、今日から快適な睡眠を手に入れましょう。
音楽が睡眠にもたらすリラックス効果
心地よい音楽には心と体をリラックスさせる効果があり、睡眠の質を高める手助けになると考えられています。音楽を聴くと私たちの脳や体は「休息モード」に切り替わりやすくなり、自律神経のうち副交感神経が優位になります。副交感神経が優位になると心拍数や血圧が穏やかに下がり、体がリラックスした状態になります。
また、心地よい音楽はストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールの分泌を抑える効果も報告されており、精神的な緊張を和らげてくれます。こうした働きにより、寝つきの悪さや不眠の症状を和らげることが期待できます。
実際に、音楽の効果は科学的にも証明されています。ある海外の研究では、就寝前にゆったりした音楽を聴くことで深い睡眠(徐波睡眠)の時間が延び、睡眠全体の質が向上したと報告されています。また、厚生労働省が紹介している2022年のレビュー研究でも、音楽を聴くことは不眠症の人々の主観的な睡眠の質を改善する可能性が示されています。つまり、「寝る前の音楽」がリラックス法の一つとして、科学的にも一定の効果が期待できるということです。
ただし、音楽の感じ方や効果には個人差があります。厚生労働省の睡眠ガイドラインでも、「すべての人に有効なリラックス法はなく、ある人に有効でも別の人にはかえって刺激となる場合もある」と指摘されています。音楽でリラックスできるかは人それぞれですので、自分に合った方法かどうか確かめることが大切です。心地よく感じる音楽であればリラックス効果が高まりやすい一方、好みに合わない曲だとかえって気になって眠れなくなることもあります。音楽以外の香りやストレッチなどと同様、自分に合ったリラックス法を見つけることが快眠への第一歩と言えるでしょう。
音楽が睡眠に良い影響を与えるポイント
- 副交感神経が優位でリラックス促進:穏やかな音楽は自律神経を整え、心拍や血圧を下げて入眠しやすい状態にします。
- ストレス軽減:音楽を聴くとストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が抑えられ、精神的な緊張が和らぎます。
- 睡眠の質向上:研究により、就寝前の音楽鑑賞が深い眠りの時間を延ばし、主観的な睡眠の質を改善するとの報告があります。
- 個人差に注意:音楽の効果は人によって異なります。自分が心地よいと感じる音楽を選ぶことが重要で、合わない曲は逆効果になる場合もあります。
参考リンク:
睡眠に適した音楽の種類と選び方
一口に「睡眠に良い音楽」と言っても、ジャンルや曲調はさまざまです。大切なのはリラックスできる音であることですが、その具体的な特徴や選び方のポイントを見ていきましょう。自分の好みやライフスタイルに合った音楽を選ぶことで、より高いリラックス効果が期待できます。
リラックスできる音楽の共通点
快眠を促す音楽にはいくつかの共通した特徴があります。第一に、テンポがゆったりとして穏やかな曲調であることです。一般的に、睡眠用の音楽は通常のポップスなどに比べてテンポが遅く、音量も小さめで抑えられています。さらに、歌詞のないインストゥルメンタルであることもポイントです。歌詞がある曲だと言葉の内容に意識が向いてしまい、脳が休まらなくなるため、就寝時には歌詞なしのBGMが適しています。
実際、世界的な研究でも睡眠に使われる音楽は「静かでスローなテンポ」「歌詞なし(器楽曲)」「アコースティック楽器による演奏」といった傾向があることが報告されています。つまり、静かでゆるやかな音の流れが心身を落ち着かせ、眠りに誘いやすいのです。
また、音楽の持つ周波数や音響特性も眠りへの影響があります。例えば、自然界の音に含まれる1/fゆらぎ(エフぶんのいちゆらぎ)と呼ばれる不規則なリズムは、人の心拍や呼吸のリズムと調和しやすくリラックス効果を高めます。川のせせらぎや波の音、小鳥のさえずりといった自然音を取り入れたヒーリングミュージックは、その1/fゆらぎにより脳をアルファ波状態へ導き、心地よい眠気を誘う代表例です。
実際にアルファ波(8~13Hzの脳波)は人がリラックスして目を閉じているときに多く出現する波であり、穏やかなクラシック音楽やせせらぎ音などはアルファ波を起こしやすいことが知られています。
要するに、睡眠に適した音楽の条件としては「ゆっくりしたテンポ」「穏やかなメロディ」「歌詞がないこと」「適度な静かさ」「自然なゆらぎや心地よい周波数を含むこと」などが挙げられます。それらの要素を満たす音楽であれば、自律神経を落ち着かせ、スムーズな入眠を手助けしてくれるでしょう。
ジャンル別・場面別のおすすめ音楽
では具体的に、どのようなジャンルの音楽が快眠に向いているのでしょうか。いくつか代表的なジャンルや場面別におすすめ音楽を紹介します。
ヒーリングミュージック・ニューエイジ系
リラックス用に作られたヒーリング音楽は、柔らかなシンセサイザーの音やゆったりとした旋律が特徴です。森林や海辺の環境音と音楽を組み合わせたものも多く、ストレスを解消し心を穏やかにしてくれます。仕事で疲れた日やストレスを感じるときに最適なBGMでしょう。
例えばピアノやハープのゆっくりした独奏曲、環境音入りのアンビエントミュージックなどは副交感神経を刺激して深い眠りへ誘う効果が期待できます。
自然音・環境音
雨の音、波の音、森林のざわめき、虫の声、焚き火のパチパチといった自然の環境音は、私たちに元来備わった安心感を呼び覚まします。これらは繰り返しのパターンや1/fゆらぎを持つため心拍を安定させ、心身をリラックス状態にします。
ホワイトノイズ(一定のシャーという音)や小川のせせらぎのような単調な音も、周囲の物音をかき消してくれるので神経質で物音が気になる方に向いています。静かすぎると落ち着かない人は、このような環境音系BGMを流すと安心して眠りにつきやすくなるでしょう。
クラシック音楽
古典的なクラシックは安定したリズムと美しいメロディを持つ曲が多く、睡眠導入に適した曲がたくさんあります。特にモーツァルトやバッハのゆるやかな楽章、ショパンのノクターン(夜想曲)などは有名な安眠クラシックです。
クラシック音楽は強弱が極端に激しすぎない曲を選ぶのがコツです。静かなピアノ曲、弦楽のアダージョ(緩徐楽章)などは心を落ち着かせ、昔から親しまれている旋律には安心感もあります。
オルゴール音(オルゴール調に編曲された曲)も音域が限られた優しい音色で、自律神経を整える効果が高いとされています。赤ちゃんの寝かしつけにもオルゴール曲がよく使われますが、大人にとっても郷愁を誘う優しい音でリラックスできます。
周波数音楽・ソルフェジオ周波数
近年、「528Hz」や「432Hz」といった特定の周波数を含む音楽が"癒しの周波数"として話題になることがあります。528Hzはソルフェジオ周波数と呼ばれ、「愛の周波数」などとも称されリラックス効果があるとされます。
また4000Hz以上の高周波音が含まれる音楽が快眠に効果的という説もあり、実際に高周波音によってストレスホルモン低下が確認された例もあります。これらの周波数音楽は科学的根拠が発展途上の分野ではありますが、「聴いて気持ちが安らぐ」と感じるのであれば取り入れてみても良いでしょう。
脳波に働きかけるα波音源やバイノーラルビート(左右でわずかに異なる周波数の音を聴かせて脳に特定の周波数の振動を起こす技法)なども、市販の睡眠導入音源として提供されています。ただし効果には個人差があるため、「なんとなく落ち着く」と思えるかどうかを基準に、自分に合うものを選ぶことをおすすめします。
年代・状況に応じた音楽選びのヒント
人それぞれ好みや置かれた状況は異なりますが、年代や状況ごとに音楽選びのヒントを挙げます。
例えば子どもの寝かしつけにはシンプルで優しいメロディの子守唄やオルゴール音楽が適しています。赤ちゃん向けには胎内音に近いホワイトノイズやゆっくりした子守唄が安心感を与えるでしょう。
一方、高齢の方で眠りが浅い場合は、若い頃に親しんだ昭和の歌謡曲のオルゴールバージョンなども安心感をもたらすことがあります。自分の好きだった曲がゆっくりしたアレンジで流れると心が落ち着くものです。
日中ストレスフルに過ごしている働き盛り世代であれば、癒やし系のアンビエント音楽や環境音がおすすめです。仕事脳から解放されるには歌詞のないゆったりBGMで頭を空っぽにする時間が有効です。特に長時間デスクワークで疲れた夜は、低音域の響きが豊かな癒し音楽(ディープなシンセサウンドやゆったりしたギター音など)は体の緊張を解きほぐし、深い眠りを促してくれるでしょう。
結局のところ、「このジャンルが絶対によい」というものではなく、自分が聴いていて心地良いと感じる音こそが最適な睡眠音楽です。いくつか試しながら、自分にピッタリの一曲やプレイリストを見つけてみてください。
参考リンク:
睡眠用BGMの具体例・おすすめリスト
ここでは、実際にどのような音楽を聴けばよいのか、具体的なおすすめ例を挙げてみます。市販のCDやサブスクリプションサービス、無料で聴けるオンライン音源など、活用できるものはたくさんあります。自分のお気に入りを見つける参考にしてください。
定番の安眠音楽・プレイリスト
Spotifyの公式プレイリスト
「Sleep」「Deep Sleep」など、Spotifyには睡眠向けの公式プレイリストがいくつも用意されています。例えば【Sleep | Spotify】ではリラックスできるピアノやアンビエント音楽が集められており、数百万ユーザーに利用されています。スマホやPCで「睡眠 音楽」などと検索すれば、他にも「おやすみ音楽」「Night Rain」など様々なプレイリストが見つかるでしょう。
YouTubeの長時間BGM動画
YouTubeでも「睡眠用BGM」「8時間 音楽」などと検索すると、寝ながら聴ける長時間再生の音源が多数出てきます。例えば、雨音だけが8時間流れ続ける動画や、ピアノの即興演奏に波の音を重ねたもの、528Hzと称するヒーリング音楽のライブ配信などバリエーションは豊富です。
寝る前にスマホで再生し、画面はオフにしておけば音だけ流れます。ただしYouTubeを使う場合は間に広告が入らないよう、プレミアムサービスを利用するかタイマー設定で動画が睡眠中に止まる工夫をすると良いでしょう(突然大きな音の広告が流れると台無しなので注意)。
定番アルバム・曲
もし特定のアルバムや曲で探すなら、以下のような定番もおすすめです。
カフェ・ミュージック系
昼間のカフェで流れるようなおしゃれで落ち着いたインストBGMは、程よい心地よさで睡眠前にも最適です。ジャズピアノのバラード集やアコースティック・ギターのインスト曲集などが該当します。
クラシックの名曲集
ショパン「子守歌」、ドビュッシー「月の光」、グリーグ「夕べの祈り」など、穏やかなクラシック名曲は安眠のお供にぴったりです。クラシック専門の無料アプリやラジオを流しっぱなしにしておくのも手軽でしょう。
環境音CD
市販のヒーリングCDには、森林やせせらぎなど自然音のみを高音質で収録したものもあります。機器を使わずCDプレーヤーで再生したい方には、そうした環境音専門のCDも根強い人気です。「小川のせせらぎ」「波音リラックス」といったタイトルで販売されています。
場面に合わせた活用アイデア
寝る30分前から流す
音楽を聴くタイミングとして、布団に入る直前より少し前(就寝30分くらい前)から流し始めるのがおすすめです。リラックス音楽を聴きながらストレッチや読書をして過ごし、「そろそろ寝る時間だよ」と脳にシグナルを送るイメージです。そのまま音楽とともにベッドに入れば、スムーズに睡眠モードへ移行できます。
スピーカーで穏やかに流す
音の聴き方も工夫しましょう。イヤホンやヘッドホンで聴くと耳を塞いでしまい長時間では耳が痛くなったり圧迫感があります。可能であればスマートフォンや小型スピーカーから直接音を流し、部屋全体を包むような形でBGMを流すと良いです。
最近はピロースピーカー(枕の中に仕込む薄型スピーカー)も市販されていますので、どうしても周囲を静かに保ちたい場合は活用するとよいでしょう。
音楽アプリのタイマー機能
多くの音楽アプリや再生デバイスにはスリープタイマー機能があります。寝入りに音楽を聴きたいけれど一晩中つけっぱなしは避けたい、という場合はタイマー設定で1時間後に停止など自動で音楽をオフにすると安心です。途中で止まっても気にならない人は流しっぱなしでも構いませんが、睡眠の深い周期に入った後は無音の方が体は完全休息できるとも言われます。心配な方はタイマーを活用しましょう。
参考リンク:
音楽を聴きながら寝る際の注意点
音楽は上手に使えば快眠に役立ちますが、使い方を間違うとかえって睡眠を妨げることにもなりかねません。最後に、音楽を聴きながら眠る際の注意点や、安全に利用するためのコツを押さえておきましょう。
音量は小さく、耳に優しく
まず一番重要なのは音量の設定です。リラックス効果を得ようとついボリュームを上げてしまうと、逆に脳が刺激されて興奮状態になり、眠りが浅くなってしまいます。就寝時に適した音量の目安はささやき声程度(およそ40デシベル以下)と言われます。図書館の中や静かな夜の住宅街くらいの静けさをイメージしてください。「小さすぎるかな?」と感じるくらい控えめで丁度良いです。
それ以上の大きな音で長時間聴くことは、睡眠の質を下げるだけでなくイヤホン難聴など耳への負担にもつながります。実際、厚生労働省の資料でも「過度に大きな音での音楽鑑賞は騒音性難聴のリスクがある」と注意喚起されています。快適な睡眠のため、音量は必ず控えめにしましょう。
また、イヤホンやヘッドホンの使い方にも注意が必要です。耳を塞ぐタイプのイヤホンを長時間つけっぱなしで寝てしまうと、耳への圧迫や蒸れによる炎症、最悪コードが首に巻き付く危険などもゼロではありません。音楽を聴きながら寝落ちしたい場合は、できるだけイヤホンは使用せずスピーカーで流すことをおすすめします。
どうしても難しい場合は、耳に負担の少ない睡眠用イヤホン(通称「寝ホン」)を使うか、寝返りで外れる前提で片耳だけつけるなど工夫しましょう。いずれにせよ耳を休ませるため、イヤホンで聴く場合はタイマーで途中停止させるか、眠りに落ちたら自動で音が消える仕組みを作っておくと安心です。
曲の選び方・避けるべき音
快眠のためには選曲も重要です。いくら好きな曲でも、テンポが速かったり刺激的すぎる音楽は寝る前には避けましょう。例えば激しいロックやEDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)など、強いビートを持つ曲は交感神経を刺激して心拍数を上げ、かえって脳を興奮させてしまいます。
就寝前にそうした音楽を聴くと「ノリが良くて気分が高揚してきてしまい、目が冴えて眠れない...」という事態になりかねません。実際、不眠症の方への指導でも就寝前の強い刺激(音や光)は避けるよう勧められています。リラックス目的で音楽を使うなら、穏やかで心地よい音だけを選ぶようにしましょう。
また、音楽そのものではありませんが、夜間の環境音にも注意です。音楽再生中でなくとも、テレビのつけっぱなしや人の話し声などは睡眠の妨げになります。どうしても静かすぎると不安な場合は前述のように自然音BGMをタイマー付きで流すなどし、深夜に突然騒がしい音が入らない工夫をしてください。最近ではスマートフォンのアプリでホワイトノイズや環境音を流せるものも多く出ていますので、活用するのも手です。
音楽+快眠環境のトータルケアを
音楽だけでなく、睡眠環境全体を整えることで安眠効果は一層高まります。音楽でリラックスできても、部屋が明るすぎたり寒すぎたりすれば熟睡は難しくなります。できる範囲で構いませんので、寝室の照明は暖色系の薄暗いライトにする、室温・湿度を快適に保つ(夏は26~28℃程度、冬は16℃前後、湿度50%前後が目安)といった基本も押さえておきましょう。
音楽と並行して、寝る前にラベンダーなどのアロマを焚いてみるのも効果的です。よい香りと音楽の相乗効果でさらに副交感神経が高まり、眠りに入りやすくなります。
さらに、寝具の心地よさも忘れてはいけません。どんなに音や環境を整えても、マットレスや枕が体に合っていなければ十分な休息は取れません。体圧分散に優れた高品質なマットレスは寝姿勢を正しく保ち、筋肉の緊張を和らげてくれます。
実際、寝室環境に関する研究でも「環境を少し変えるだけで睡眠の質が大きく変化する」と述べられており、静かな音楽や香りとともに良質な寝具に包まれることが快眠のカギだとされています。音楽+BGMの力と快適な寝室環境の両方を味方につけて、ぐっすり眠れる夜を増やしていきましょう。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。