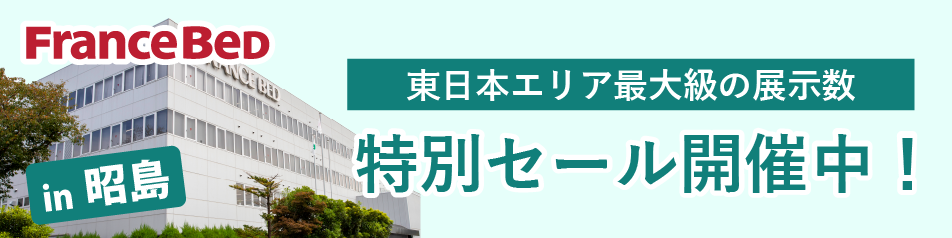.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
分割睡眠のメリット・デメリットとは?質の高い睡眠をとるためのポイントを解説
公開日:2025.08.17(日)
仕事や育児で夜に十分眠れず、「夜4時間+昼2時間」のように睡眠を分けている人は多いでしょう。このような分割睡眠は忙しい現代人にとって仕方のない工夫ですが、「健康に問題はないの?」「連続で眠らなくても疲れは取れるの?」と心配になりますよね。
この記事では分割睡眠のメリット・デメリットを分かりやすく解説し、質の高い睡眠をとるためのコツや効果的な仮眠の取り方も紹介します。
分割睡眠とは?基本的な知識
分割睡眠とは、1日の睡眠時間を2回以上に分けてとる睡眠スタイルのことです。例えば夜に数時間眠って、昼間に短い仮眠を取るケースが代表的です。
実は昔の人々にとって、夜中に一度起きて再び眠る「二相性睡眠」は珍しいことではありませんでした。電気がなかった19世紀以前の冬など、長い夜の間に一度起きて読書や談笑をし、また寝床に戻るという習慣が記録されています。
つまり、睡眠を分けること自体は人類にとって新しい現象ではないのです。しかし現代社会では夜間にまとめて眠る単相性睡眠が基本とされており、成人は通常、夜間に連続して眠ることが理想的とされています。
有名人の短時間睡眠エピソード
歴史上の偉人では「ナポレオンは1日3時間しか眠らなかった」「エジソンは睡眠を無駄と考えて4時間程度しか寝なかった」など、極端に短い睡眠で活躍した話が有名です。
こうした話を聞くと、「成功者は睡眠時間を削っているから自分も...」と考えたくなるかもしれません。しかし注意が必要です。
実際のところ、ナポレオンは日中に居眠りや仮眠を取って睡眠不足を補っていたという説があります。エジソンも1~2時間の仮眠を複数回とって、足りない睡眠を補っていたそうです。つまり彼らは完全な睡眠不足で働き続けていたわけではなく、こまめに眠っていた可能性があります。
さらに、生まれつき非常に短い睡眠でも大丈夫なショートスリーパーは人口のわずか数%しかいない特殊な存在です。このような人々には睡眠に関わる特定の遺伝子変異が見られ、深い睡眠から素早く目覚められる体質だと報告されています。
裏を返せば、そうした遺伝子を持たない大多数の人が偉人の真似をして睡眠時間を削れば、単なる慢性睡眠不足に陥って健康を害するだけだと専門家は警告しています。
分割睡眠のデメリット・リスク
分割睡眠を続けることには、科学的に様々なデメリットや健康リスクが指摘されています。ここでは断続的な睡眠がもたらす主な悪影響を見ていきましょう。
集中力・記憶力の低下
睡眠が細切れになると脳の休息が十分でなくなりがちです。頻繁に睡眠が中断されることで、注意力や記憶力、判断力といった脳の働きが低下しやすくなります。
結果として日中の仕事や学習のパフォーマンスが著しく落ち、ミスが増える恐れがあります。実際、大学生を対象とした研究では、合計睡眠時間が同じでも分割睡眠グループの方が成績の低下を招いたとの報告があります。
このように断続的な睡眠は脳の働きを鈍らせ、生産性を下げる要因となってしまいます。
生活習慣病などのリスク増加
長期的な睡眠不足や断続的な睡眠は、生活習慣病のリスクを高めることが研究で示されています。十分な連続睡眠が取れない状態が続くと、ホルモンバランスや代謝のリズムが乱れ、肥満や糖尿病、高血圧などの発症につながりやすくなります。
実際に1日の睡眠時間が7時間未満の人では、記憶障害や糖尿病のリスクが有意に高まることが分かっています。また睡眠不足によって本来夜間に低下するはずの血圧が下がらず、心臓への負担が増大するとの指摘もあります。
厚生労働省の睡眠指針でも、成人の適切な睡眠時間はおおむね6~8時間とされ、6時間未満や8時間超の人は病気のリスクが高まると報告されています。
体内時計の乱れによる不調
人間の体は概日リズム(サーカディアンリズム)によって、眠気や体温、ホルモン分泌のサイクルが24時間周期で調整されています。睡眠時間帯が不規則になったり分割されたりすると、この体内時計のリズムが乱れてしまいます。
その結果、日中に本来最大限発揮できるはずの集中力や作業効率が低下したり、学習した情報の記憶定着が妨げられる可能性があります。特に夜型の生活や交代勤務で睡眠リズムが不規則になると、糖代謝や心血管への負担が増すことも報告されています。
分割睡眠は体内時計を狂わせ、体と脳のパフォーマンスに広い影響を与える点にも注意が必要です。
ストレス増加・メンタルへの影響
十分な連続睡眠が取れない状態が続くと、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が増加しやすくなることが知られています。断片的な睡眠しかとれない生活では、朝の目覚めに強い疲労感が残ったり、日中も疲れやイライラが募りやすくなります。
これにより気分の落ち込みや不安感が増してメンタルヘルスに悪影響を与える可能性があります。慢性的な寝不足状態はうつ病など精神的な病気のリスク要因にもなりえますし、ストレスが溜まることで人間関係にも悪影響が出るかもしれません。
睡眠不足が続くと自制心も弱くなり、結果的に生活習慣の乱れ(夜間の飲食や飲酒の増加など)によってさらに睡眠の質が下がる悪循環に陥る恐れもあります。
起床回数の増加による心身への負担
分割睡眠では眠りと起きる回数が増えるため、そのたびに心身へかかる負荷も積み重なります。人間にとって起床は交感神経が活発になり心拍数や血圧が上がる刺激的な行為です。
夜中に何度も起きて再び寝直す生活は、心臓や血管に対する負担となり、長期的には心血管疾患のリスクを高める可能性があります。また各睡眠サイクルが短すぎると深い眠り(徐波睡眠)に十分到達できず、疲労が取りきれないまま次の活動に移ることになりかねません。
起きる回数が増えることで「また早く寝付かなければ」と焦りが生まれ、かえって精神的なストレスになるケースもあります。つまり睡眠を小刻みに分割すること自体が心身への余計な負担となり、睡眠の質を総合的に低下させてしまう恐れがあるのです。
分割睡眠のメリットや有効なケース
ここまで分割睡眠のデメリットを見てきましたが、一方で状況次第ではメリットが得られる場合もあります。一般論としては連続した十分な睡眠に越したことはありませんが、以下のようなケースでは分割睡眠もうまく活用する価値があるでしょう。
仕事や勤務上の都合
夜勤や超多忙な業務でまとまった睡眠時間を確保しにくい場合、合計睡眠時間が短くなっても途中で仮眠をとることで集中力を維持できる可能性があります。
例えば夜勤労働者が勤務中に2時間ほど仮眠をとれば、眠気によるミスを減らしパフォーマンスを向上させる効果が期待されます。やむを得ず睡眠時間を削らなければならない場面では、分割睡眠が次善の策として役立つでしょう。
一時的な不眠症への対処
夜中に何度も目が覚めてしまうタイプの不眠症の人にとって、「途中で起きても良い」と発想を転換して敢えて二度寝前提のスケジュールにすると、かえって精神的ストレスが軽減される場合があります。
実際、専門家の見解では夜中に目覚めても「これは普通のこと」と受け入れることで落胆や焦りが減り、結果的にまた眠りに戻りやすくなるとされています。このように分割睡眠を一時的に取り入れて睡眠への過度な不安を和らげ、その後再び通常の睡眠リズムに戻していくといった不眠症克服の手段も提案されています。
戦略的な仮眠で効率アップ
日中のパワーナップ(短時間の仮眠)を積極的に活用することで、総睡眠時間を減らしつつ覚醒時間を増やそうとする取り組みがあります。有名な例では、サッカー選手クリスティアーノ・ロナウドが90分睡眠を1日5回繰り返す特殊な睡眠法を実践していることで知られています。
これはプロのトレーナー監修のもと厳密なルールで行われている手法で、一般人には真似できませんが、トップアスリートの中には競技パフォーマンス向上のために分割睡眠を取り入れるケースも報告されています。
このように分割睡眠は一般人の健康維持には基本的に適しませんが、特定の状況下では一時的な助けとなることもあります。重要なのは、自分の置かれた状況と体調を客観的に判断し、必要に応じて分割睡眠を取り入れつつ、できるだけ早めに通常の睡眠パターンに戻すよう努めることです。
分割睡眠を上手に乗り切るコツ・質を高める工夫
どうしても睡眠を分割せざるを得ない場合でも、いくつかの工夫を凝らすことで負担を軽減し、睡眠の質をできるだけ確保することが可能です。以下に断続的な睡眠生活を乗り切るための具体的なポイントを紹介します。
効率的な仮眠(パワーナップ)の取り方
日中に短い仮眠を取ることは、眠気の解消や作業効率アップに非常に有効です。ただし仮眠の取り方を間違えるとかえって寝起きにぼんやりしたり、夜の睡眠に支障が出ることもあります。
効果的なパワーナップのために、次の点に注意しましょう。
仮眠のタイミング
起床から約7~8時間後、午後の早い時間帯に仮眠するのがおすすめです。例えば朝6時に起きているなら14時前後が適切なタイミングです。それより遅い時間に仮眠をとると夜の寝つきが悪くなる可能性があります。
仮眠時間の長さ
15~20分程度の短時間にとどめましょう。20分以上眠ってしまうと脳が深い睡眠に入ってしまい、目覚めがかえって悪くなります。短時間で目覚めれば頭がスッキリし、眠気だけを効率的に解消できます。
寝る場所・姿勢
本格的にベッドに入るより、椅子に座るかソファで軽く横になる程度に留める方が良いでしょう。体を横たえると深く眠り込みやすくなるため、意図的に浅い睡眠で留める工夫です。オフィスで仮眠するならデスクに突っ伏して寝るくらいがちょうど良い場合もあります。
環境を整える
短時間でもリラックスできるよう、必要に応じてアイマスクや耳栓を使って光や音を遮断しましょう。エアコンの音などホワイトノイズを適度に利用すると周囲の雑音を意識せずに済むこともあります。上着やブランケットで体を冷やさないようにするのも大切です。
寝る前のカフェイン摂取
仮眠前にコーヒーや緑茶など適量のカフェインを摂っておくと、20分ほどでカフェイン効果が現れ始めるため、目覚める頃にちょうど頭がシャキッとします。いわゆる「コーヒーナップ」と呼ばれる方法で、深く寝入ってしまうのを防ぐ効果も期待できます。
ただし夕方以降の仮眠ではかえって夜の睡眠に影響する可能性があるため、このテクニックは午後の早い時間帯までに留めましょう。
睡眠の質を高める生活習慣と寝具選び
分割睡眠のデメリットを補うには、各睡眠機会の質をできるだけ高めることが重要です。日頃の生活習慣や睡眠環境を見直し、少ない睡眠でも深く熟睡できる工夫を取り入れましょう。
規則正しい生活リズム
分割睡眠でも毎日できるだけ同じ時刻に寝起きすることで、体内時計の乱れを最小限に抑えます。平日と休日で極端に睡眠スケジュールを変えないようにし、体に一貫したリズムを刻ませましょう。
朝の光を活用
起床後はすぐに太陽の光を浴びて体内時計をリセットします。朝日を浴びると脳が覚醒して夜に眠くなるタイミングが整いやすくなります。短時間睡眠でも朝の光を習慣化することでメリハリのある覚醒モードを維持できます。
適度な運動習慣
日中に軽い運動やストレッチを行いましょう。体を動かすことで深部体温が上昇し、その後の下降期にスムーズな入眠が促されます。また運動による心地よい疲労感は深い睡眠をもたらしやすくなります。
デスクワーク中心で体を使わない人ほど意識的に体を動かすことが大切です。
就寝前の過ごし方
分割睡眠で眠りに入るチャンスが限られている分、寝る前の準備が肝心です。就寝前1~2時間はリラックス時間とし、テレビやスマホなど強い光刺激を発する電子機器の使用を控えましょう。
ブルーライトは脳を覚醒させ寝つきを悪くします。代わりに読書やストレッチ、軽い音楽、ぬるめの入浴など心身を落ち着かせる習慣を取り入れてください。就寝直前のカフェインやアルコール、喫煙も睡眠の質を下げる原因になるので避けましょう。
寝具・睡眠環境の最適化
短い睡眠でも質を上げるには、快適な寝室環境を整えることが欠かせません。室内は暗く静かにし、エアコンや加湿器で適温・適度な湿度に調整しましょう。
そして何より自分に合った寝具(マットレスや枕)を使うことが重要です。体格や姿勢に適したマットレスは体圧を分散して体をしっかり支え、睡眠中の不要な寝返りや体の痛みを減らしてくれます。
例えば国内老舗メーカーの日本ベッドが採用する超高密度ポケットコイル構造のマットレスは、寝ている間の細かな体の動きにもきめ細かくフィットするため、浅い眠りの原因となる体への違和感や圧迫感を軽減してくれます。
また世界的ブランドのシモンズなどの高品質マットレスも体のラインに沿った抜群のサポート力で知られ、短時間でも深い眠りに入りやすくする手助けとなるでしょう。枕も高さや硬さが合っていないと睡眠の質を損ねるため、自分に合うものを選んでください。
寝具を見直すことは睡眠環境への投資であり、分割睡眠で不足しがちな快眠を補う強力な味方となります。
まとめ:分割睡眠と上手に付き合うために
忙しさや事情でどうしても分割睡眠になってしまう場合もあるかもしれませんが、基本的には連続した十分な睡眠に勝るものはありません。
分割睡眠には集中力低下や健康リスク増加など多くのデメリットがあるため、可能であれば生活リズムを調整してまとまった睡眠時間を確保することが望ましいでしょう。厚生労働省の指針でも一般成人は1日あたり7時間前後の睡眠が推奨されており、睡眠時間が足りない状態が長く続けば心身に少なからぬ悪影響が蓄積します。
とはいえ現実には、夜まとめて長時間眠れない人々も多く存在します。そのような場合はこの記事で紹介したように仮眠のテクニックを駆使したり、睡眠環境を整えて各睡眠の質を高める工夫を行いましょう。
短時間の昼寝を上手に取り入れることで眠気をリセットし、パフォーマンス低下を防げることもあります。また「自分だけが変則的な睡眠で困っているのではないか」と思い詰めず、必要以上に不安を募らせないことも大切です。
結論として、分割睡眠そのものは理想的とは言えないものの、工夫次第で乗り切ることは可能です。できる範囲で生活リズムを調整し、質の高い睡眠習慣と環境を追求することで、断続的な睡眠による弊害を最小限に抑えられるでしょう。
十分な睡眠が取れていないと感じる方は、今回紹介したポイントをぜひ実践してみてください。日中の眠気や疲労感が和らぎ、限られた睡眠時間でも以前よりすっきりとした目覚めを得られるはずです。
そして可能であれば、将来的にまとまった睡眠を確保できるライフスタイルへと少しずつシフトしていくことをおすすめします。質の良い睡眠は心身の健康と日々のパフォーマンスを支える土台です。自分にとって最適な眠り方を追求し、健やかな毎日を送りましょう。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。