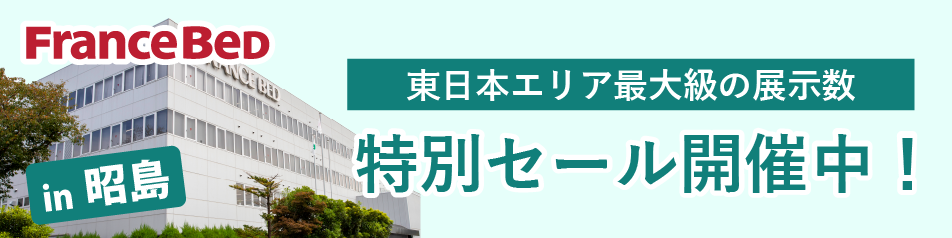.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
睡眠サイクルとは?90分周期のメカニズムを科学的に解説|快眠のコツ
公開日:2025.09.21(日)
毎晩の眠りには一定のリズムがあることをご存知でしょうか。人間の睡眠はノンレム睡眠(脳を休ませる深い眠り)とレム睡眠(夢を見る浅い眠り)が交互に繰り返される睡眠サイクルで成り立っています。1サイクルは約90分とされ、一晩にこのサイクルを4〜6回程度繰り返しながら、眠りの深さや夢を見るタイミングが変化していきます。
この記事では、人間の睡眠サイクルの基本的な仕組みを分かりやすく解説します。また、よく聞く「睡眠は90分周期だから○○時間寝ればいい」といった話の真偽についても検証し、本当に質の良い睡眠を得るための実践的なコツをご紹介します。
毎朝すっきりと目覚めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
ノンレム睡眠とレム睡眠の違い
眠っている間、私たちの脳と体はノンレム睡眠とレム睡眠という2種類の状態を周期的に繰り返しています。それぞれ脳や身体の働きが大きく異なる睡眠のタイプで、脳波や体の反応にも違いが現れます。
レム睡眠(Rapid Eye Movementの略)では、脳が起きている時と同じくらい活発に働きます。この時に夢を見たり、日中の記憶を整理・定着させたりしています。
一方、ノンレム睡眠では大脳がしっかりと休息しており、脳や体の疲労回復には欠かせない時間です。睡眠中に分泌される成長ホルモンの多くは深いノンレム睡眠時に放出され、細胞の修復や免疫機能の向上を促します。
このようにノンレム睡眠は主に身体の休養・修復を、レム睡眠は脳の整理・準備という大切な役割を担っています。
ノンレム睡眠の3つのステージ
ノンレム睡眠は眠りの深さに応じてステージ1(N1)、ステージ2(N2)、ステージ3(N3)の3段階に分かれます。
ステージ1(N1)は寝入りばな(うとうと状態)の段階で、周囲の音などで簡単に目が覚めてしまう浅い眠りです。
ステージ2(N2)に入ると意識がなくなり、呼吸や脈拍が規則的になります。比較的浅い睡眠ですが、全睡眠時間の中で最も長い時間を占めています。
ステージ3(N3)は徐波睡眠とも呼ばれ、脳波が大きくゆっくりしたデルタ波となる最も深い眠りの段階です。この時、筋肉の力が抜けて体が完全にリラックスしています。成長ホルモンの分泌が特に活発になるのもステージ3の深い睡眠中で、身体の修復・成長にとって重要な時間です。
深い眠りの最中に揺り動かされても簡単には目覚めず、仮に起こされても頭がぼんやりしてすぐには活動できないほど眠りが深い状態となります。
睡眠サイクルの仕組み
私たちが眠りについてから目覚めるまでの流れ(睡眠サイクル)は、ノンレム睡眠とレム睡眠がセットになって約90分を1つの単位とするリズムで進んでいきます。
まず就寝後はノンレム睡眠に入り、ステージ1からステージ2を経てステージ3の深い眠りに到達します。入眠から30分〜1時間ほどで一番深いところまで達すると、その後は再び睡眠が浅くなってステージ2相当まで戻り、続いて最初のレム睡眠が現れます。これで1回の睡眠周期(約90分)が完了です。
その後は再びノンレム睡眠に入って次のサイクルが始まり、この90分前後の周期が夜間に繰り返されます。
一晩の睡眠サイクルの変化
一般的な成人の場合、一晩(6〜8時間程度)の睡眠で4〜6回の睡眠サイクルが進行します。各サイクルの中で現れるレム睡眠とノンレム睡眠の割合は、夜が進むにつれて変化していきます。
夜の前半(就寝直後から数時間)は深いノンレム睡眠(ステージ3)が多く現れ、後半になるにつれてレム睡眠の時間が長くなる傾向があります。
つまり、最初の2〜3サイクルでは深い眠りに集中し、朝方に近づく4〜5サイクル目には夢を見るレム睡眠が増えて浅い眠りが中心になるということです。このような睡眠の構造変化は、体にとって効率よく回復と準備を行うための自然な仕組みだと考えられています。
「90分周期で起床すれば目覚めが良い」は本当?
「睡眠時間は90分の倍数にすると目覚めが良い」という話を聞いたことがある方は多いでしょう。これは、人間の睡眠が約90分周期で区切られているなら、その区切れ目(レム睡眠が終わったタイミング)で起床すればスッキリ目覚められるはず、という考え方に基づいています。
確かに、睡眠中に深いノンレム睡眠の最中であるステージ3で起こされると、強い眠気やだるさ(睡眠慣性)に襲われやすくなります。逆にレム睡眠のタイミングでは脳が覚醒に近い状態のため、比較的目覚めやすい傾向があります。
個人差が大きい睡眠サイクル
しかし実際には、睡眠サイクルの長さやリズムには大きな個人差があり、誰もが常に「90分きっかり」のリズムで眠っているわけではありません。
研究によると、一人ひとりの睡眠周期は約60分〜120分と幅があることが確認されており、90分という数値はあくまで平均的な例に過ぎません。またレム睡眠が現れるタイミングも、その人の体内時計や睡眠不足の有無、就寝時刻のずれ、お酒の影響などによって前後することが分かっています。
たとえば、いつもより遅い時刻に就寝した場合、本来は序盤には出現しないはずのレム睡眠が異例に早く現れることもあり、こうなると「90分周期」が簡単にずれてしまいます。
専門家の見解
このように現実の睡眠は常に一定のリズムで進むわけではないため、「90分単位で睡眠時間を調整すれば誰でも快適に起きられる」というほど単純なものではありません。
結論として、90分の倍数で寝起きすれば必ず目覚めが良いと断言することはできない、というのが専門家の共通した見解です。それよりも、十分な睡眠時間を確保し、毎日規則正しい時刻に就寝・起床することで睡眠リズムそのものを安定させることが、結果的に朝の目覚めを良くする近道になります。
睡眠不足が続けば、どのみち眠りの質が低下してしまい、どのタイミングで起きてもだるさが残ってしまいます。まずは自分に必要な睡眠時間をしっかり確保し、体内時計に従った生活リズムを維持することが大切といえるでしょう。
良質な睡眠を得るためのポイント
ここからは、睡眠サイクルの知識を日々の生活で活用するために、睡眠の質を高めるコツをご紹介します。日頃の習慣や環境を見直し、小さな工夫を積み重ねることで、深い睡眠とスッキリした目覚めを手に入れましょう。
規則正しい生活リズムを保つ
平日・休日を問わず、毎日できるだけ同じ時間に就寝・起床することで、体内時計が安定し睡眠サイクルも整いやすくなります。
平日の睡眠不足を週末にまとめて補おうとする寝だめは、かえって体内リズムを乱してしまうため避けましょう。休日に長く寝ないといけないほど平日に眠れていないというサインでもあるため、まずは日々必要な睡眠時間を確保することが重要です。
十分な睡眠時間を確保する
質の良い睡眠の大前提として、必要な長さの睡眠をきちんと取ることが欠かせません。一般的に成人では7〜9時間程度の睡眠が推奨されており、少なくとも6時間以上は毎日眠るよう心がけましょう。
個人差はありますが、多くの人にとって5時間未満の睡眠では慢性的に睡眠不足となってしまいます。十分な長さの睡眠を取ることで各サイクルの後半に現れるレム睡眠までしっかり得られ、心身の回復と記憶整理が十分になされます。
就寝前の習慣に気をつける
眠りにつく前の行動次第で、寝つきの良さや睡眠の深さが変わってきます。
寝る直前までスマートフォンやパソコンの画面を見ていると、強い光によって脳が昼間と勘違いしてしまい、寝つきが悪くなる恐れがあります。また、夜遅くのカフェイン摂取や喫煙も脳を刺激して睡眠を妨げる要因です。
就寝前1〜2時間はリラックスできる環境を整え、照明を落として静かな時間を過ごすよう意識しましょう。軽いストレッチや読書、音楽鑑賞など自分なりのリラックス法を取り入れるのもおすすめです。
心身がスムーズに眠りのモードへ移行することで、深いノンレム睡眠に入りやすくなります。
快眠をサポートする寝具選び
人間の眠りは心身の状態だけでなく、睡眠環境にも大きく左右されます。なかでも毎晩身体を預ける寝具(マットレス・枕・掛け布団など)は、睡眠の質に直結する重要な要素です。
実際に、寝具を適切なものに替えただけで睡眠の質が向上したケースも多く報告されています。自分に合った寝具を選ぶことは快眠への投資といえるでしょう。
マットレス・敷布団の硬さ
体が沈み込みすぎず、硬すぎない適度な硬さの寝具を選ぶことが重要です。
柔らかすぎるマットレスでは腰や背中が深く沈み込んで不自然な姿勢になり、逆に硬すぎる寝具では身体への圧迫が強くなって血行が妨げられ、熟睡しにくくなります。理想は、立っている時の姿勢に近い自然な寝姿勢を保てる硬さです。
自分の身体にフィットし、頭から背中・お尻まで体の重さをバランス良く分散して支えてくれるマットレスであれば、睡眠中の体への負担が軽減され、深い眠りを妨げにくくなります。
実際、マットレスの反発力や構造によって寝返りのしやすさに違いが生じ、それが睡眠の質に影響を与えることが研究で示されています。過度に身体が沈むタイプで寝返りが打ちにくい寝具よりも、必要に応じてスムーズに寝返りできる寝具の方が、途中で目覚めにくく快適な睡眠につながります。
枕の高さ・形状
自分の体格に合った枕を使うことも、良い睡眠には欠かせません。首や肩に無理のない高さ・形状の枕を選ぶことで、寝ている間も自然な首のカーブを保ちやすくなります。
人によって首のカーブや肩幅・頭の大きさは異なるため、本当に合った枕の高さは一人ひとり違います。高すぎる枕を使うと顎が引けた姿勢になって首や肩の筋肉に負担がかかり、逆に低すぎると頭が後方に落ち込んで気道が圧迫されるため呼吸がしにくくなります。
このように合わない枕は睡眠中の身体にストレスを与え、眠りの質を低下させる一因となります。仰向けだけでなく横向きに寝た時も肩と頭の間にすき間ができないよう、十分な厚みと弾力のある枕が理想的です。
掛け布団と寝室の環境
睡眠中の体温変化を快適にコントロールするには、掛け布団や寝室の環境にも気を配りましょう。
人は眠りについた後、深い睡眠に入る頃に身体の内部の温度(深部体温)が下がります。これは体内から熱を放出することで脳を冷やし、深い眠りを維持しやすくするための自然な反応です。
この時、寝具が寒すぎたり通気性が悪すぎたりすると体が冷えすぎてしまい、快適な眠りが妨げられます。したがって、掛け布団は保温性が高く適度に体にフィットするものを選び、睡眠中にかいた汗を吸収・発散してくれる吸湿・放湿性にも優れた素材が理想です。
季節や個人差にもよりますが、一般的に寝床内の温度は約33℃、湿度は50%程度に保たれると快適だとされています。冬場で寝具が冷えていると体が緊張して寝つきにくくなるため、就寝前に湯たんぽや電気毛布などで布団を適度に温めておくのも効果的でしょう。
質の高い寝具で睡眠サイクルを整える
以上のようなポイントを踏まえ、自分に合った寝具を選ぶことで睡眠の質は大きく向上します。
例えば、シモンズやシーリー、サータといった世界的トップブランドのマットレスは、体圧分散や耐久性に優れ、理想の寝姿勢をサポートする高品質な製品として知られています。また、昭和西川のムアツ布団や日本ベッド、フランスベッドなど国内メーカーの寝具にも、最新の睡眠工学に基づく工夫が凝らされています。
それぞれ特徴は異なりますが、自身の体格や寝姿に合った寝具を選び、適切にメンテナンス(マットレスのローテーションや枕の交換など)しながら使うことで、長期間にわたり質の高い睡眠サイクルを維持できるでしょう。
まとめ
人間の睡眠は約90分周期のサイクルで構成され、ノンレム睡眠(深い睡眠)とレム睡眠(浅い睡眠)が1セットになって一晩に4〜6回繰り返されます。前半ほど深い眠りが多く、朝に向かうにつれてレム睡眠が増えていくのが特徴です。
ノンレム睡眠には深さの異なる3つのステージ(N1〜N3)があり、浅い眠りのステージ1・2と、成長ホルモンが分泌されるような深い眠りのステージ3に分かれます。レム睡眠は身体は休んでいるものの脳が活発に動いて夢を見る段階で、心身を覚醒状態に準備させる役割があります。
睡眠周期には個人差があり、必ずしも全員が90分ピタリのリズムで眠っているわけではありません。人によってサイクル長は1時間程度から2時間近くまで幅があり、また体内リズムや生活習慣によっても変動します。
そのため「90分の倍数で起きれば誰でも快適に目覚められる」という訳ではなく、十分な睡眠時間を確保した上で自分に合ったリズムを見つけることが大切です。
快適な目覚めのためには睡眠の質を高めることが重要です。そのために毎日必要な睡眠時間(成人で7〜9時間が目安)を確保し、平日も休日もできるだけ規則正しい生活リズムを守るようにしましょう。就寝前の強い光やカフェイン摂取を避け、リラックスした状態で眠りにつく工夫も効果的です。
寝具や寝室環境を整えることで睡眠の質をさらに向上させることができます。自分の体格や好みに合った寝具(マットレス・枕・布団)を使うことで、無理のない姿勢でぐっすり眠ることができます。特にマットレスは硬さや反発力が睡眠中の身体への負担を左右するため、体圧分散に優れ寝返りしやすいものを選ぶとよいでしょう。
質の高い睡眠を実現するために、まずは今回ご紹介したポイントから取り組んでみてはいかがでしょうか。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。