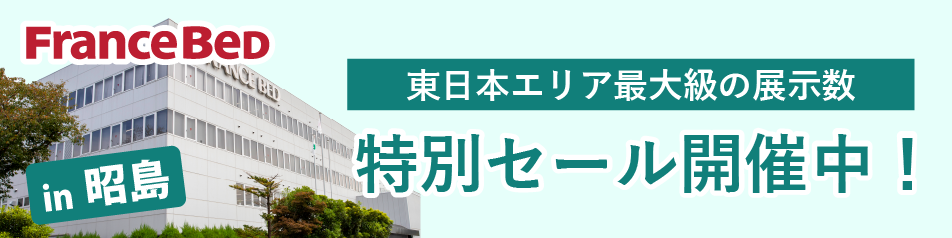.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
睡眠用耳栓の選び方とおすすめ|メリット・デメリットと安全な使い方
公開日:2025.07.05(Sat)
夜中の騒音やパートナーのいびきで眠れず、困っていませんか?静かな環境で眠りたいけれど、「耳栓をしたら目覚ましに気づかないかも…」「長時間つけて耳が痛くならない?」と心配な方も多いでしょう。
実は睡眠用耳栓は、街の騒音やいびき対策として効果があるだけでなく、音に敏感な人の安眠グッズとしても注目されています。この記事では、睡眠用耳栓の効果や正しい使い方、安全性について詳しく説明し、あなたに合った耳栓の選び方やおすすめのタイプもご紹介します。耳栓を上手に使って、快適な睡眠環境を手に入れましょう。
睡眠中の騒音による影響と耳栓の必要性
私たちが気持ちよく眠るためには、できるだけ静かな環境を作ることが大切です。一般的に35~40dB以下の静けさが理想とされ、それより大きな音があると睡眠が邪魔される可能性があります。
例えば、普通の会話の音は約50~60dB、エアコンの室外機でも約40~60dBの音が出るため、こうした日常の音でも睡眠の妨げになってしまいます。都市部の夜は車の音や近所の生活音で図書館並み(40dB)を超えることも多く、眠りが浅くなったり途中で目が覚めたりする原因となります。
耳栓を使うと耳に入る音の大きさを大幅に小さくでき、睡眠中に感じる周りの騒音レベルを理想的な静けさに近づけることができます。ある調査では、耳栓を使う理由の約6割が安眠のためだったというデータもあります。このことからも、多くの人にとって騒音対策として耳栓が快適な睡眠に役立つ有効な道具であることがわかります。
さらに、音にとても敏感なHSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)の方にとって、睡眠時のわずかな物音でもストレスになります。HSP気質の人は小さな物音でも気になってしまい眠れないことがあり、その対策の一つとして耳栓で雑音をシャットアウトするといった工夫が推奨されています。不快な音刺激を遮断し安心できる環境を作るためにも、自分に合った耳栓を活用する価値は大いにあるでしょう。
睡眠用耳栓を使うメリット
雑音を遮断して睡眠の質を向上できる
睡眠用耳栓の最大のメリットは、周囲の雑音を大幅に遮断できる点です。耳栓をすることで急な物音や続く騒音を和らげ、眠りやすく深い睡眠を得られるようサポートしてくれます。例えば隣の部屋のテレビ音や同居人のいびきに悩まされている場合でも、耳栓をつければそうした音を気にせず眠りに集中でき、結果として睡眠の質が向上するでしょう。
また、耳栓はストレス軽減にもつながります。夜中に騒音で何度も起こされると睡眠不足になるだけでなく、「また音がしたらどうしよう」と構えてしまい心身がリラックスできません。耳栓であらかじめ音を遮断しておけば安心感が生まれ、心地よい眠りを妨げる不安要素を減らすことができます。十分な睡眠が取れるようになると日中の集中力や気分も改善し、精神的・身体的な健康にも良い影響を与えるでしょう。
手軽でコストパフォーマンスの高い防音対策
耳栓はドラッグストアやインターネットで手軽に手に入れることができ、価格も安いのも大きなメリットです。寝室の騒音対策として防音カーテンの設置や窓の二重サッシ化なども効果的ですが、これらは工事や高額な費用がかかります。その点、耳栓であれば数百円程度から買うことができ、購入してすぐその夜から使い始めることができます。
さらに、耳栓は小さくて持ち運びしやすいため、旅行先や出張先のホテルなど環境が変わる場所でも役立ちます。飛行機や夜行バスなど移動中に睡眠を取りたいときにもサッと使えるため、さまざまな場面で活躍する安眠グッズとして重宝するでしょう。このように、睡眠用耳栓は費用対効果が高く、誰でもすぐ始められる騒音対策の切り札と言えます。
メリットのポイント
- 睡眠環境の静音化: 耳栓で周囲の騒音をカットし、深い睡眠と快適な目覚めにつながる
- 手軽さと即効性: 安価で手に入れやすく、思い立った時にすぐ使える手軽な防音対策
- ストレス軽減: 騒音による中途覚醒を防ぎ、安心感を得ることで睡眠中のストレスを軽減できる
睡眠用耳栓のデメリットと注意点
便利な睡眠用耳栓ですが、使い方によってはデメリットや注意すべき点もあります。以下に主な注意点をまとめます。
耳の健康へのリスク(外耳炎など)
耳栓を長時間続けて使ったり、汚れた状態で繰り返し使い続けたりすると、耳の中の健康を損ねる恐れがあります。特に注意したいのが外耳炎(外耳道炎)です。外耳炎とは耳の穴から鼓膜までの外耳道の皮膚に炎症が起こる病気で、痛みやかゆみ、場合によっては耳だれ(分泌物)や聞こえにくさを引き起こします。汚れた耳栓を使い続けることはこの外耳炎のリスクを高めると指摘されています。
千葉市医師会も「不衛生な耳栓や補聴器の継続使用は外耳道炎の発症リスクを高める」と警告しています。耳栓は直接耳の中に入れるものですから、使い捨てタイプは早めに新品に交換し、繰り返し使えるタイプでも定期的に洗浄・消毒して清潔を保つことが大切です。
また、耳栓の使い方が間違っていると耳の皮膚を傷つけることがあります。耳栓を無理に奥まで押し込み過ぎたり、耳穴より大きすぎるサイズのものを使ったりすると、耳の内部の皮膚に傷がついて炎症の原因になる場合があります。特に就寝時は長時間つけっぱなしになるため、耳に負担を感じないフィット感のものを選び、違和感がある場合は無理に使い続けないようにしましょう。
音に気づきにくくなる不安
耳栓で周囲の音を遮断すると、目覚まし時計や火災報知機といった重要な音に気づきにくくなるデメリットもあります。朝の目覚ましに遅れてしまわないか心配で耳栓の使用をためらう方もいるでしょう。
この対策としては、耳栓をしながらでも聞こえる大音量のアラームを設定する、スマートウォッチやスマートフォンのバイブレーション機能で起床する、あるいは片耳だけ耳栓をする方法などがあります。最近では必要な音だけ通すデジタル耳栓も登場しており、騒音は遮りつつアラーム音や人の呼びかけ声は聞こえるよう調整できる製品もあります。不安な場合はこうした工夫を凝らし、自分に合った起床方法と併用すると良いでしょう。
慣れによる依存や心理的な不安
耳栓に慣れてしまうと、「耳栓がないと眠れない」と感じるようになる人もいます。これはデメリットというより心理的な依存ですが、旅行先で耳栓を忘れて寝付けなくなるといったケースも考えられます。普段から耳栓を使用する場合でも、時には耳栓なしで寝てみたり、ホワイトノイズを流して眠るなど耳栓以外の方法にも慣れておくと安心です。
また、耳栓をつけていることで逆に「周囲の音が全く聞こえない状態」が不安になる方もいます。そのような場合は、完全遮音タイプではなく適度に音を通す低減タイプの耳栓や、ヒーリング音を流す安眠マシンの併用など、自分がリラックスできる方法を探ってみましょう。
デメリット・注意点のまとめ
- 外耳炎などのリスク: 汚れた耳栓の使用や長時間の連用は耳の炎症を招く恐れ。常に清潔を心がける
- 警報音に気づきにくい: 目覚ましや非常時の音が聞こえにくくなる。不安な場合は大音量アラームや振動目覚ましを併用
- 装着感の問題: サイズが合わなかったり押し込みすぎで耳を傷つける恐れ。痛み・かゆみを感じたら使用を中止し、フィットする別タイプを検討
睡眠用耳栓の種類と選び方
睡眠用耳栓には様々な種類があり、それぞれ特徴や適した用途が異なります。自分に合った耳栓を選ぶために、主な耳栓のタイプと選択時のポイントを押さえておきましょう。
主な耳栓の種類
フォーム(低反発ウレタン)タイプ 一般的なスポンジ状の耳栓で、指で潰して耳穴に入れるとゆっくり膨らんでフィットします。遮音性が高く柔らかな着け心地が特長で、長時間つけても圧迫感が少ないため睡眠時にも使いやすいタイプです。使い捨てが基本ですが安価で手に入りやすく、騒音対策の入門としてまず試すのに適しています。
フランジ(ひれ)タイプ シリコンやゴム製で複数の傘状のひれ(フランジ)が付いた耳栓です。中央に芯があり着脱しやすく、耳に入る部分に指が直接触れない構造なので衛生的に使えます。水洗いも可能で繰り返し使えますが、遮音性能はフォームタイプに比べやや劣る傾向があります。素材がやや硬めのものが多く、長時間装着すると耳が痛くなる場合があるため、睡眠時より作業用や水泳用に向いています。
シリコン粘土タイプ 柔らかいシリコン樹脂を粘土のように指でこねて耳の穴をふさぐタイプです。耳穴の入口に貼り付けるように使い、耳の形に自在にフィットして密閉できるのが特長です。耳の中に差し込まないので圧迫感や異物感が少なく、耳道が小さい方や「耳に物を入れるのは苦手」という方にも使いやすいタイプです。ただし粘着性が高いため、寝返り時に髪の毛や布団のホコリが付着しやすく、お手入れに気を遣う必要があります。
デジタル(電子)耳栓タイプ 最近登場した電子機器型の耳栓で、ノイズキャンセリング機能を搭載したイヤホンのような製品です。周囲の騒音のみを打ち消しつつ、人の声やアラーム音など必要な音は聞こえるよう調整できる高度な耳栓です。外音取り込み機能を備えたものもあり、耳栓による安心感を得ながら会話やアナウンスも聞き逃しません。ただし価格が高価で充電などの手間もかかるため、主に在宅勤務中の集中用途やどうしても完全防音が必要な場合に選択肢となるでしょう。
その他特殊用途タイプ 飛行機の離着陸時の気圧変化から耳を守る「気圧調整用耳栓」や、水泳・シャワー時に耳への水の浸入を防ぐ「防水タイプ」など、用途に特化した耳栓もあります。睡眠用途ではあまり使用しませんが、必要に応じて使い分けましょう。
耳栓を選ぶポイント
1. 遮音性能(ノイズ減衰量)をチェック 耳栓の商品パッケージには「NRR値」や「SNR値」といった数値が記載されています。これは耳栓が何dBの音を小さくできるかを示す指標で、値が大きいほど高い遮音性を持ちます。例えばNRRが30dBの耳栓であれば、70dBの騒音環境を約40dBまで下げられる計算です。騒音レベルが高い環境で使うほど、高い遮音性能を持つ耳栓が必要になります。ただし遮音性が高いほど耳栓自体が大きく硬めになる傾向もあるため、必要十分な遮音性能と装着感のバランスで選ぶことが重要です。
2. 耳へのフィット感・快適性 長時間つけて眠る場合は、つけ心地の良さがとても大切です。耳栓の素材によって柔らかさや弾力が異なるため、自分の耳に合う素材を選びましょう。一般的に、低反発フォームは柔らかく耳への負担が少ない反面汚れやすいので使い捨てが無難、シリコンやエラストマー素材は洗えて経済的ですが圧迫感を感じやすい場合もあります。また耳栓のサイズも人それぞれ耳穴の大きさが違うため、レギュラーサイズで痛い場合は小さめサイズの商品(女性・子供向け)を試すと良いでしょう。
3. 睡眠時の姿勢への適合 仰向けだけでなく横向きで眠る方は、耳栓の形状にも注意しましょう。耳からはみ出す部分が大きいと、横向きに寝たとき枕に当たって痛みを感じることがあります。フランジタイプや電子耳栓は出っ張りがあるものが多いため、横向き寝が多い人には低反発フォームタイプや粘土タイプなど耳穴に収まりやすいものが向いています。寝返りを打っても外れにくく、耳が圧迫されない形状かどうかも選定時に確認すると良いでしょう。
4. メンテナンス性と経済性 繰り返し使えるタイプの耳栓は経済的ですが、その分お手入れの手間がかかります。シリコンやフランジタイプは使用後に毎回水洗いやアルコール消毒をすると清潔に保てます。一方、フォームタイプは基本使い捨てで衛生的ですが、使い捨てる頻度によってはランニングコストがかさむ場合もあります。衛生管理とコストのバランスを考えて、自分が無理なく続けられるタイプを選びましょう。
睡眠用耳栓の正しい使い方
耳栓の効果を十分に得るためには、正しいつけ方とお手入れ方法を理解しておくことが大切です。以下に、フォームタイプ耳栓を例とした基本的な装着手順と、使用時の注意点をまとめます。
耳栓の基本的な装着方法
- 手を清潔にする 耳栓を触る前に石けんでよく手を洗いましょう。耳栓に雑菌が付着するのを防ぐためです。
- 耳栓を細く圧縮する フォームタイプの耳栓は指でつまんで細長く圧縮します。硬めのフォームの場合、指先で転がすようにしてしっかり細くしましょう。このとき、清潔な手で行うのはもちろん、圧縮した耳栓が元に戻る前に素早く耳に入れる準備をします。
- 耳を引っ張りながら挿入 片手で圧縮した耳栓を持ち、反対の手で装着する側の耳たぶ(耳の上部)を上後方に軽く引っぱります。これは耳の穴の形状をまっすぐにして、耳栓を奥まで入れやすくするためです。耳を引っぱった状態のまま、ゆっくりと耳栓を耳穴に「優しく」挿入します。乱暴に押し込むと耳道を傷つける恐れがあるので注意してください。
- フィットするまで保持 耳栓を挿入したら指を離し、フォームが膨らんで耳穴に密着するのを感じます。完全に膨らんでフィットするまで数秒間、そのまま耳栓を軽く押さえて固定しましょう。しっかりと密閉されると周囲の音が遠く小さく聞こえるようになります。
- 正しく装着できたか確認 鏡で見て耳栓の大部分が耳の中に収まっているか確認します。違和感が強い場合や痛みを感じる場合は一度外して挿入し直すか、サイズ・種類を変えてみてください。
使用時と使用後のケア
清潔な状態を保つ 耳栓装着前は手を洗うだけでなく、耳自体も清潔にしておきましょう。耳垢が多くたまっていると耳栓で押し込んでしまう恐れがあるため、綿棒などで優しく耳の入口付近を掃除しておくと良いです。ただし耳掃除のしすぎも外耳炎の原因となるため注意が必要です。
外すときもゆっくり丁寧に 起床時や耳栓を外す際は、いきなり引っ張らずゆっくりひねりながら引き出すようにしましょう。急に抜くと鼓膜に負担がかかったり、フォームタイプの場合は真空状態になって耳を傷めることがあります。
お手入れと保管 使い捨てタイプは基本的に一度使ったら新しいものに交換するのが理想です。特に就寝時に長時間使ったものは汗や皮脂を含んで雑菌が繁殖しやすいため、ケチらず交換しましょう。繰り返し使えるタイプは、使用後に表面をアルコール消毒したり、水洗い可能なものは中性石鹸で洗ってよく乾かしてください。
違和感を感じたら使用を中止 着用中に少しでも耳に痛みやかゆみ、圧迫される感じがあれば無理に使い続けないでください。耳栓はあくまで快適に眠るための道具ですので、我慢してつけるものではありません。別のサイズや素材に替えてみて、それでも不快感が続くようなら専門医に相談しましょう。
耳栓以外で静かな睡眠環境を作るには
耳栓は騒音対策として非常に効果的ですが、併せて寝室環境全体を整えることも快眠には重要です。耳栓と組み合わせたり、耳栓が苦手な方でも実践できる静かな睡眠環境づくりの工夫をいくつかご紹介します。
ホワイトノイズの活用
「静かすぎると逆に些細な物音が気になって眠れない」という方には、ホワイトノイズを流す方法が有効です。ホワイトノイズとはテレビの砂嵐音やエアコンの音のような一定のシャーという音で、周囲の不規則な物音を覆い隠す「音のカーテン」の役割を果たします。
スマートフォンのアプリや専用の安眠マシンで小川のせせらぎや雨音など心地よいホワイトノイズを流しながら寝ると、突然の物音が気になりにくくなりリラックスできるでしょう。耳栓と併用してボリュームを調整すれば、自分にとって丁度良い静けさを演出できます。ただし音量は小さめに設定し、逆にうるさくならないよう注意してください。
寝室の防音対策
物理的な防音対策も睡眠環境改善に効果的です。例えば厚手の遮音カーテンを設置すれば、窓から入る車の走行音や深夜の生活音を減らすことができます。また、窓やドアの隙間にテープやモールを貼って音漏れを防ぐ簡易防音も有効です。
寝具を工夫するのも一案です。例えば高反発マットレスや横向き寝専用枕を使っていびきを軽減できれば、そもそもの騒音発生を抑えられます。パートナーのいびき対策としては、仰向けだといびきをかきやすいので横向きに寝てもらうよう促したり、鼻孔拡張テープを活用してもらう方法もあります。本人だけでなく周囲の人の睡眠の質向上にもつながるでしょう。
心理的な安心感づくり
騒音に敏感で眠れない方は、精神的な緊張を和らげる工夫も大切です。就寝前にストレッチや深呼吸をしてリラックス状態を作ったり、アロマオイルで好きな香りを焚いて副交感神経を優位にするのも有効です。音に関して不安が強い場合、「多少の物音があっても自分は眠れる」と自己暗示をかけるのも心理的に違います。
耳栓を「これで大丈夫」というお守り代わりに考え、多少の音は気にしない心構えでベッドに入ると、かえってすっと眠りに入れることもあります。
おすすめの睡眠用耳栓(タイプ別)
最後に、あなたのニーズに合わせたおすすめの睡眠用耳栓のタイプを整理してみましょう。以下のような目的・好みに当てはまる方は、それぞれ記載の耳栓タイプを試してみてください。
最大限の遮音性が欲しい人 「とにかく騒音をシャットアウトして静寂を得たい」という方には、低反発フォームタイプ耳栓がおすすめです。高い遮音性能でいびきや交通騒音を大幅に軽減できます。柔らかい素材で長時間つけても耳が痛くなりにくく、睡眠用の定番と言えるでしょう。
装着感の優しさを重視する人 耳への圧迫感や異物感が苦手な方、耳の穴が小さい方には、シリコン粘土タイプ耳栓がおすすめです。耳穴の入口をふんわり覆うだけなので、付けているのを忘れるほど快適なフィット感があります。密閉性も高く遮音効果もしっかり得られるため、ストレスなく静かな環境を作りたい人に向いています。
必要な音は聞き取りたい人 耳栓で騒音だけカットしつつ、目覚ましや家族の声など肝心な音は聞こえるようにしたい方は、デジタル耳栓(ノイズキャンセリング耳栓)が選択肢になります。周囲の騒音成分だけを打ち消す電子的な仕組みで、静寂と安全を両立できます。値段は高くなりますが、高性能な快眠ツールとして検討してみてもよいでしょう。
コストをかけず試してみたい人 初めて耳栓を使う方や、まずはお金をかけずに効果を試したいという方には、ドラッグストアで買える使い捨てフォーム耳栓が無難です。数百円で数ペア入りの商品も多く、まず試してみて合わなければ別タイプに切り替えることも容易です。耳栓は相性がありますので、安価なもので色々試して自分にピッタリの一品を見つけるのも良いでしょう。
まとめ:耳栓を活用して質の高い睡眠を
睡眠用耳栓は、騒音に悩む現代人にとって手軽で効果的な快眠アイテムです。正しく使えば耳への悪影響の心配もほとんどなく、静かな環境でぐっすり眠る手助けとなってくれるでしょう。
都市部の騒音や隣のいびきに悩まされている方、音に敏感で眠りが浅いと感じている方は、ぜひ耳栓の力を試してみてください。ただし耳栓に頼るだけでなく、睡眠環境全体の改善や生活リズムの見直しも並行して行うことで、より一層質の高い睡眠が得られるはずです。
快適な睡眠は心身の健康の土台です。耳栓を上手に取り入れて、夜の静寂と安らぎを手に入れ、毎朝爽やかな目覚めを迎えましょう。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。