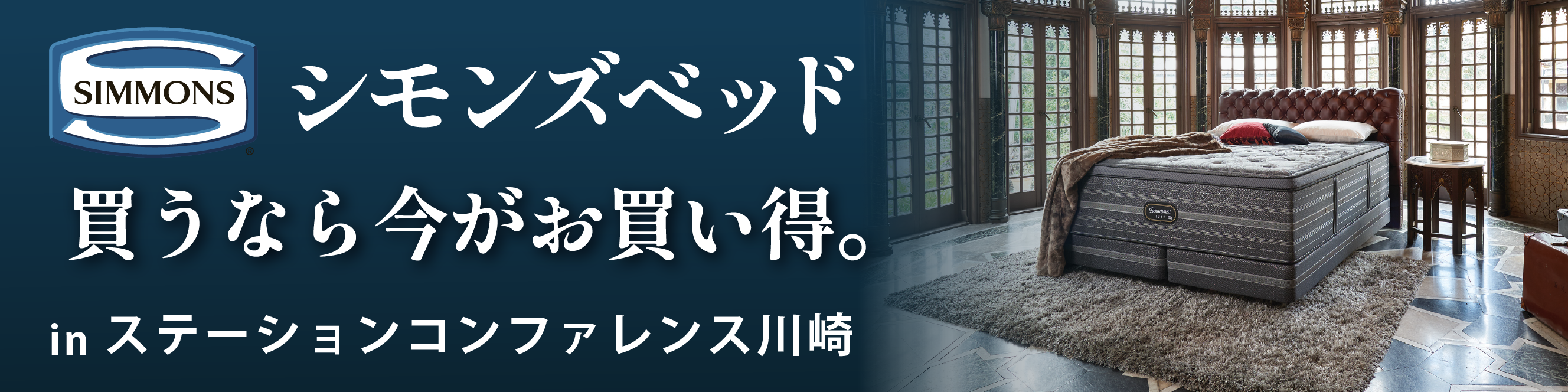.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
5時間睡眠は大丈夫?健康への影響と質の高い眠りのコツ
公開日:2025.07.05(Sat)
平日は毎日5時間ほどしか眠れず、「将来、体を壊してしまうのではないか」と心配していませんか。一般的に十分な睡眠時間は7~8時間程度と言われていますが、忙しい現代人にとって、それだけの時間を確保するのは難しいことも多いでしょう。
この記事では、5時間睡眠が体に与える影響や健康への危険性について、最新の研究結果をもとにわかりやすく説明します。
また、睡眠時間が短くても睡眠の質を高める方法や、昼間の眠気を乗り切るコツなど、毎日を元気に過ごすためのポイントも紹介します。短い睡眠時間とうまく付き合いながら、将来の健康への不安を軽くしていきましょう。
必要な睡眠時間は人それぞれ
「理想の睡眠時間」は一概に何時間とは言えません。
個人差が大きく、人によって必要な睡眠時間は違うからです。一般的に成人の場合、一晩に7時間前後眠る人が多く、6~8時間程度が標準的な範囲とされています。実際、日本人の平均睡眠時間はおよそ7時間強と報告されています。
しかし、大切なのは「その人にとって十分な睡眠かどうか」です。睡眠時間が同じでも、昼間に眠気やだるさを感じずに活動できていれば、その人にとって適切な睡眠が取れていると考えられます。逆に、7~8時間眠っていても昼間に強い眠気があれば、その人には足りていない可能性もあります。
ショートスリーパーとロングスリーパー
世の中には、とても短い睡眠時間でも元気に生活できる人たちがいます。「ショートスリーパー」と呼ばれる人々で、一般的に一晩3~5時間程度の睡眠でも昼間に支障がない特殊なタイプです。逆に「ロングスリーパー」は10時間以上眠らないと調子が出ない人を指します。
このように必要な睡眠時間には個人差がありますが、ショートスリーパーは人口のごくわずかな特殊な存在です。最近の研究では、ショートスリーパーには短時間睡眠でも質の高い睡眠をとれる遺伝的な特徴がある可能性も報告されています。
実際、ショートスリーパーの家系を調べた研究では、目覚めを促す特定の遺伝子(β1-アドレナリン受容体遺伝子)の変異が見つかっています。こうした遺伝的要因により、生まれつき短時間睡眠でも平気な体質の人がいる一方で、大部分の人にとって5時間睡眠は本来必要な睡眠量に足りず、何らかの無理をしている状態と考えるべきでしょう。
なお、年齢を重ねると必要な睡眠時間は多少短くなる傾向があります。一般的に20代と比べて60代では必要睡眠時間が約1時間ほど短くなると言われています。年齢を重ねると新陳代謝が下がり、若い頃より長時間の睡眠を必要としなくなるためです。
ただし、高齢になると眠りが浅くなり、途中で目が覚めやすくなる傾向もあります。そのため、「年を取ったら長く眠れなくなるのは自然なこと」と考えて、昼間に支障がなければあまり心配しすぎる必要はありません。
要点まとめ: 眠りに必要な時間には個人差があります。5時間睡眠で足りるかどうかは人それぞれですが、多くの人にとって5時間は短すぎます。ごくまれに短時間でも問題ない体質の人(ショートスリーパー)もいますが、基本的には「昼間に眠気や不調がないか」を目安に、自分に合った睡眠時間を見極めましょう。
5時間睡眠を続けるとどうなる?体への影響
「5時間しか寝ていないけど、大丈夫なのだろうか?」――この疑問に答えるには、その5時間が自分にとって睡眠不足かどうかがポイントです。必要な睡眠量に対して明らかに足りていない場合、体には少しずつ様々な負担がたまっていきます。
ここでは短い睡眠時間が続くことによる体への影響を、昼間の状態から将来的な健康への危険性まで順に見てみましょう。
昼間の集中力低下・眠気やパフォーマンスへの影響
十分な睡眠が取れていないと、翌日の昼間にさまざまな不調が現れます。代表的なのが強い眠気や集中力の低下です。寝不足の翌日は頭がぼんやりして仕事や勉強に身が入らない、といった経験をお持ちの方も多いでしょう。
これは睡眠不足によって脳が十分に休息できず、認知機能が低下しているためです。研究によると、健康な大人でも2日間続けて4時間睡眠になるだけで、注意力・判断力が著しく低下することが確認されています。
慢性的な睡眠不足状態では記憶力の低下ややる気・気力の減退も起こりやすくなります。実際、1日5時間程度の睡眠を1週間続けると、もはや徹夜明けと同じ程度まで作業能力が低下するとの報告もあります。
怖いのは、睡眠不足が当たり前になると脳がその状態に「慣れて」しまい、能力が落ちていても本人の感じる眠気はそれほど強くなくなることです。つまり、知らず知らずのうちに仕事の効率が下がり、ミスや事故の危険性が高まってしまう可能性があります。
十分な睡眠を取った日と比べて寝不足の日は、判断力・反射神経も鈍り、注意力散漫になることが様々な実験で示されています。重大な事故の背景にドライバーや作業者の睡眠不足があった例も少なくありません。
5時間睡眠が続いて昼間に強い眠気や集中困難を感じる場合、それは体が休息を求めているサインです。コーヒーや気合いでごまかしながら活動を続けるのは危険と言えるでしょう。
ホルモンバランスの乱れと生活習慣病の危険性の上昇
睡眠不足は当日の眠気だけでなく、体内のホルモン分泌や自律神経の働きにも大きな影響を与えます。具体的には、慢性的に睡眠が不足すると食欲に関わるホルモンのバランスが崩れることが知られています。
例えば、満腹感を促す「レプチン」というホルモンの分泌が減少し、食欲を増進させる「グレリン」というホルモンが過剰に分泌されることが報告されています。その結果、寝不足が続くと普段より食欲が増してしまい、つい食べ過ぎて太りやすくなる可能性があります。
また、睡眠中に休まるはずの交感神経が高ぶったままになる影響で、インスリンの効き目が悪くなり(インスリン抵抗性の増大)、同じ食事をしても血糖値が下がりにくくなることも分かっています。つまり、睡眠不足は太りやすさや糖代謝の悪化を招きやすい状態なのです。
こうした変化により、長期間の睡眠不足は生活習慣病の危険性を高めることが多数の研究で明らかになっています。実際に、慢性的に1日5~6時間未満の短い睡眠しかとらない人は、十分に睡眠をとっている人に比べて2型糖尿病の発症率が高いことや、高血圧症を発症しやすいことが報告されています。
睡眠不足が続くと本来夜間に下がるはずの血圧が高いままになるなど、心血管系にも負担がかかります。さらに、睡眠不足状態では体の免疫力が低下し、炎症反応が起こりやすくなることも分かってきました。これは風邪をひきやすくなるだけでなく、動脈硬化の進行など生活習慣病の悪化要因にもなります。
こうした理由から、アメリカ心臓協会(AHA)では心血管の健康管理に「適切な睡眠時間の確保」を重要項目に加えるなど、睡眠不足は世界的にも重大な健康上の危険要因として位置づけられています。
平日5時間睡眠が続いている方は、将来の生活習慣病の危険性を高めないためにも、できる範囲で睡眠時間を延ばしたり質を改善したりする工夫が大切です。
寿命への影響は?短い睡眠と死亡の危険性の関係
「睡眠時間が短いと寿命が縮む」と耳にしたことがあるかもしれません。実は、睡眠時間そのものが直接寿命を決めるわけではないとされています。ただし前述の通り、短い睡眠が続くと生活習慣病をはじめ様々な病気にかかる危険性が高まり、結果的に健康寿命を縮めてしまう可能性があります。
近年の大規模調査でも、睡眠時間と死亡率にはU字型の関係(短すぎても長すぎても死亡の危険性が上昇する傾向)が報告されています。国内の約10万人を長期間追跡した研究では、1日あたり睡眠時間が4時間以下の人は、7時間眠る人に比べて総死亡リスク(全ての原因による死亡率)が約1.3倍に高まるとの結果が示されました。5時間程度の睡眠でも「短め」の部類に入り、多少なりとも死亡の危険性が上昇している可能性があります。
また、健康寿命に関係する興味深いデータとして、複数の慢性疾患を抱える危険性と睡眠時間の関連があります。イギリスで行われたホワイトホールIIという公衆衛生調査によれば、50歳時点で睡眠時間が5時間以下の人は、7時間睡眠の人に比べて、その後25年間で2つ以上の慢性疾患(例えば糖尿病と心臓病など)を併発する危険性が約30%高かったと報告されています。
このように短い睡眠習慣は将来的な複合的健康リスク(複数の病気を同時に患う危険性)につながる可能性が指摘されており、その延長線上で寿命にも影響しうると考えられます。
もっとも、一概に「毎日7時間寝れば長生きできる」というほど単純ではない点には注意が必要です。睡眠時間が短い人でも他の生活習慣が良好で健康を維持している人もいますし、逆に長く寝ている人が必ずしも健康とは限りません。
重要なのは睡眠時間の長短だけでなく、睡眠の質や昼間の健康状態です。5時間睡眠であっても昼間快調で病気の危険要因(喫煙・肥満・運動不足など)が少なければ、大きな問題に至らないケースもあるでしょう。
ただし統計的には睡眠時間が極端に短い人ほど生活習慣病の患者数が多い傾向があるため、やはり注意を払うに越したことはありません。「自分は大丈夫」と過信せず、健康診断などで血圧・血糖などを定期的にチェックすることも大切です。
要点まとめ: 毎日5時間睡眠のような慢性的睡眠不足は、将来的に以下の危険性を高めます。
- 肥満の危険性: 食欲ホルモンバランスの乱れにより食欲が増進し、太りやすくなる可能性があります。
- 生活習慣病の危険性: 糖尿病、高血圧症、心臓病、脳卒中などの発症率が上昇します。免疫力低下や炎症促進も起こりやすくなります。
- 死亡リスクの上昇: 短すぎる睡眠は長期的に見て総死亡率を高めるとの研究があります(睡眠時間と死亡率のU字カーブ)。健康寿命を縮める要因となりえます。
- パフォーマンス低下: 昼間の強い眠気や集中力低下により、仕事や運転でミス・事故を起こす危険性が増します。
短時間睡眠でも元気に過ごすためのコツ
理想を言えば平日でも必要なだけ十分に眠るのが一番ですが、現実には仕事や育児などで「どうしても毎日5時間程度しか寝られない」という方も多いでしょう。
そんな場合でも、睡眠の質を高めたり昼間の過ごし方を工夫したりすることで、短い睡眠時間を補い元気に生活することは可能です。
このセクションでは、限られた睡眠時間の中で体と脳をしっかり休めるための具体的なコツを紹介します。
寝室環境と寝具を整える
良い睡眠のためには「環境づくり」が非常に重要です。短時間でも質の高い深い眠りを得るため、まずは寝る環境を見直してみましょう。ポイントは以下の通りです:
静かで暗い寝室: 寝室の騒音や明るさは眠りの深さに大きく影響します。夜は遮光カーテンなどで外の光を遮り、スマートフォンやLED時計の光も気にならないよう工夫しましょう。耳栓やアイマスクを活用するのも効果的です。
室温・湿度の調節: 人が快適に感じる温度・湿度で眠ることも大切です。暑すぎたり寒すぎたりすると寝つきが悪くなり、睡眠中にも何度も目が覚めてしまいます。エアコンや加湿器を使って、夏はやや涼しく(約25℃前後)、冬は寒すぎない程度(布団内が33℃程度になるのが目安)に調整しましょう。
寝具(マットレス・枕)の工夫: 自分の体に合った寝具を使うことも質の良い睡眠には欠かせません。例えばマットレスが古くへたっていたり、自分に合わない硬さで体に負担がかかっていると、熟睡を妨げる原因になります。
体に負担をかけず、寝返りがしやすい寝具を選ぶことで、短い時間でも熟睡感が得られるようになるでしょう。枕も高さや硬さが合っていないと首や肩のこわばりにつながりますので、自分にフィットするものを選んでください。
こうした睡眠環境の改善は、「短くてもぐっすり眠る」ための基本です。まずは費用をかけなくてもできる範囲で、音・光・温度などの条件を整えてみましょう。季節に応じて寝具(掛け布団の厚さ調整やパジャマの素材選び)を変えることも効果的です。
睡眠の質を高める生活習慣
毎日の生活習慣を少し意識するだけでも、夜の睡眠の深さが変わってきます。睡眠の質を上げるための主なポイントは次の通りです:
朝の光と適度な運動: 朝起きたらしっかり太陽の光を浴びましょう。朝の光は体内時計をリセットし、夜に向けて自然な眠気を促すリズムを作ります。また昼間に軽い運動を取り入れると、夜に心地よい疲労感で眠りに入りやすくなります。 (※激しい運動は就寝直前より夕方までに済ませるのがおすすめ)
就寝前のカフェイン・アルコールを控える: 寝る前のコーヒーや濃いお茶、エナジードリンクは禁物です。 カフェインは覚醒作用が長時間続き、寝つきを悪くして睡眠を浅くします。少なくとも就寝3~4時間前以降のカフェイン摂取は控えましょう。
また「お酒を飲むと眠れる」と感じる方もいるかもしれませんが、寝酒(就寝前のアルコール)は逆効果です。アルコールは入眠を助ける面もありますが、分解される過程で睡眠が浅くなり、途中で目が覚めやすくなります。深酒や喫煙も睡眠の質を下げるので避けましょう。
就寝前のリラックス習慣: 寝る直前の過ごし方にも気を配りましょう。スマートフォンやパソコンの画面から発せられるブルーライトは脳を刺激して眠気を遠ざけますので、就寝1時間前を目安に電子機器の使用はやめるのが理想です。
代わりにストレッチやヨガ、軽い読書などで心身をリラックスさせましょう。ぬるめのお湯にゆっくり浸かる入浴も体温の下降を促して寝つきを良くします。寝る直前に重い食事をとると消化にエネルギーが使われて熟睡の妨げになるため、夕食は就寝2~3時間前までに済ませ、寝る前の夜食は避けた方が無難です。
このように規則正しい生活リズムとメリハリが、結果的に夜の睡眠の質向上につながります。平日は難しくても、可能な範囲で「朝はしっかり起きて昼間活発に、夜は徐々に心身を鎮めていく」サイクルを意識してみましょう。
また、平日に不足した睡眠を週末に補おうと長く寝る方もいるでしょう。ある程度の寝坊で疲労を回復させることは有益ですが、いわゆる「寝だめ」は完全にはできないことも覚えておいてください。休日に昼過ぎまで寝すぎると体内時計がずれて、かえって月曜の朝がつらくなる場合もあります。休日の朝も平日より2~3時間以内のずれに留め、足りない分は昼寝で補う方がリズムを維持できます。
短い昼寝(パワーナップ)の活用
夜の睡眠時間が短い人にぜひ取り入れていただきたいのが、昼間の短い仮眠=「パワーナップ」です。パワーナップとはお昼過ぎの時間帯に15~30分程度だけ眠る習慣のことで、午後の眠気をリセットして脳をシャキッと目覚めさせる効果があります。
昼食後の勤務中に強烈な眠気に襲われて困った経験はありませんか?そんなとき、いっそ10~20分だけでも机に伏せて目を閉じてみましょう。短時間でも眠ると不思議と頭がすっきりし、午後の作業効率が格段に上がります。
事実、20分ほどの仮眠をとった人は全くとらなかった人に比べ、その後の課題成績が向上したという研究報告もあります。睡眠不足が続いて注意力が低下している場合には、事故防止の観点からも効果的な対策と言えるでしょう。
昼寝を効果的に行うポイントは以下の通りです:
時間帯は午後早めに: 昼過ぎの13~15時頃までにとるのが理想です。それ以降の夕方近くに寝てしまうと、夜の入眠がかえって遅くなってしまう恐れがあります。
長さは30分以内: 仮眠時間が30分を超えると深いノンレム睡眠に入ってしまい、目覚めたときにかえってぼんやりしてしまいます。10~20分程度の短い昼寝で切り上げるのがコツです。スマホのアラームをセットしておき、長く寝過ぎないようにしましょう。
環境を整える: オフィスでも可能なら目をつぶって静かに過ごせるスペースを見つけましょう。アイマスクや耳栓があるとより短時間で眠りに入りやすくなります。椅子に座ったままでも構いません。足を投げ出せるリクライニングチェアなどがあるとベストですが、デスクに伏せて目をつむるだけでも脳は休息できます。
「昼寝をすると夜眠れなくなるのでは?」と心配する人もいますが、15~20分程度の短い昼寝であれば夜の睡眠に悪影響はありません。
むしろ人間の体内リズム上、午後2時前後には軽い眠気のピークが自然と訪れるため、このタイミングで賢く仮眠をとることで夜の睡眠リズムも安定すると言われています。実際、高齢者を対象とした研究でも、昼間に30分の昼寝を習慣にしたところ、夕方以降の居眠りが減り夜間の中途覚醒も少なくなったという報告があります。
短い昼寝で昼間の眠気や疲労をリセットすれば、その後の活動がはかどるだけでなく、結果的に夜もスムーズに眠りにつけるという良いサイクルが生まれるのです。
なお、どうしても仕事中に昼寝をとるのが難しい場合は、休憩時間に5分でも目を閉じて静かに過ごすだけでも違います。 また、昼休みにコーヒーを一杯飲んですぐ仮眠すると、ちょうど20分後くらいにカフェインが効いて目覚めがシャキッとするという「コーヒーナップ」というテクニックも知られています(個人差がありますので、お好みで試してみてください)。
いずれにせよ、短時間睡眠が続く方は上手に昼の仮眠を取り入れて、睡眠不足をこまめに解消する意識を持ちましょう。
まとめ
短い睡眠時間でも工夫次第でカバーできることがお分かりいただけたでしょうか。忙しくて毎日十分には眠れない人ほど、「睡眠の質」や「昼間の過ごし方」が健康維持の鍵となります。
平日は5時間睡眠でも、週末に無理のない範囲で少し長めに眠ったりリラックスする時間を確保することも大切です。また、昼間にどうしても不調が強い場合は勤務環境の見直しや医師への相談も検討してください。
睡眠不足による不安は、正しい知識と対策でかなり和らげることができます。ぜひ今日からできることから実践し、短い睡眠時間とも上手に付き合っていきましょう。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。