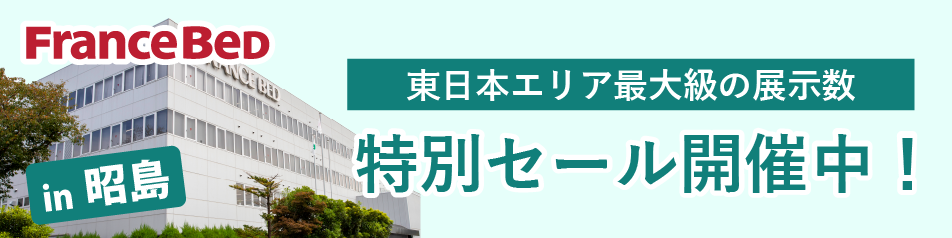.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
睡眠時の心拍数はどのくらいが正常?高い・低い時の原因と対処法
公開日:2025.08.23(Sat)
夜寝ている間の心拍数は、普段どれくらいになるものなのでしょうか。スマートウォッチなどで自分の睡眠中の心拍数を確認して、「高すぎるのでは?」「全然下がっていないけど大丈夫?」と不安に感じた経験がある方も多いでしょう。
実は睡眠中の心拍数は、私たちの体調や睡眠の質を表す重要な指標です。この記事では、睡眠時の心拍数の正常値や個人差、夜間に心拍数が異常に高くなる原因と極端に低くなる場合の注意点、そして心拍数を安定させるための改善策について詳しく解説します。
睡眠時の心拍数とは?正常な範囲と変化
睡眠中の心拍数の基本知識
睡眠時の心拍数とは、文字通り眠っている間の1分間あたりの心拍数(脈拍数)のことです。人は通常、起きて安静にしているときの心拍数(安静時心拍数)が約60~100拍/分程度と言われています。
しかし、眠りにつくと体がリラックス状態に入り、自律神経のバランスが副交感神経優位となるため、睡眠中は心拍数がさらに低下するのが一般的です。特に深い眠り(ノンレム睡眠)の間は全身が休息モードになるため、心拍数も日中よりもかなり低くなる傾向があります。
睡眠中の心拍数の正常範囲
平均的な成人の場合、睡眠中の心拍数は個人差はあるものの、安静時より下がっておおよそ40~60拍/分程度まで低下することがよく見られます。
実際、心臓病のない健康な人でも、深夜には心拍数が30台/分になるケースも珍しくありません。こうした睡眠時の徐脈(心拍が遅い状態)は生理的な現象であり、身体が十分に休息している証拠とも言えます。
運動習慣のある人やアスリートでは心拍数が低めになる傾向があり、睡眠中に60未満に下がっても正常とされています。
睡眠ステージによる心拍数の変化
一方で、レム睡眠(浅い眠り、夢を見ている状態)のときには脳が活発に動いており、交感神経が一時的に優位になるため心拍数がやや速くなることがあります。
夢の内容によってはドキドキして心拍が上がることもありますが、それも一過性で通常はすぐ落ち着きます。また、眠っている間でも寝返りや覚醒に近い浅い睡眠段階では心拍数が上下に変動します。
このように、一晩のうちでも睡眠ステージに応じて心拍数は刻々と変化しています。
正常範囲の目安
正常な範囲としては、成人の場合安静時で60~100拍/分が一般的な目安ですが、実際の健康な人の平均はそれより少し低く、65±10拍/分程度であるとの調査結果もあります。
日本人間ドック学会の基準では、45~85拍/分が"異常なし"(正常範囲)と判定され、85拍/分を超えると頻脈傾向、40拍/分未満は徐脈傾向として経過観察や精密検査が推奨されています。
ただし睡眠中に限って言えば、50拍/分を下回る徐脈状態になるのは珍しいことではなく、生理的に起こり得ます。定期健診で異常を指摘されていない健康な人なら、睡眠時に心拍数が多少低くても基本的には問題ないケースがほとんどです。
注意が必要な場合
逆に、睡眠中にも関わらず心拍数が高め(例えば80~100台)で推移する場合は、何らかの要因で体がリラックスしきれていない可能性があります。
もちろん、個々人の基礎心拍や測定状況によっても左右されるため、一概に「何拍以上なら異常」と断定はできません。しかし安静時や睡眠中に一貫して90~100以上の心拍数が続くようなら要注意です。
そのような慢性的な頻脈傾向は、心臓に負担をかけるだけでなく将来的に心疾患リスクの増加とも関連する可能性が指摘されています。したがって、自分の睡眠時平均心拍数が明らかに高すぎる場合は、その原因を探り対策していくことが大切です。
睡眠中の心拍数が高いと感じるのはなぜ?
「寝ているはずなのに心拍数が妙に高い」——そんな経験がある方もいるでしょう。通常、就寝中は心拍数が下がるものですが、何らかの原因で夜間に心拍数が上がってしまうことがあります。
睡眠中に平均80~90台/分以上の心拍数が続いていたり、夜中に急に心臓がバクバクして目が覚めるような場合には、以下のような原因が考えられます。
ストレス・不安が残っている
日中の精神的ストレスや緊張が十分に解消されないまま眠りにつくと、夜間も交感神経が高ぶった状態が続き、心拍数が下がりにくくなります。
心理的な不安や悩み事で心が休まらないと、深夜でも脳が活発に働き体がリラックスできないため、安静時にも心臓がドキドキと頻脈気味になることがあります。特に仕事のプレッシャーや緊張状態が慢性的に続いていると、自律神経の乱れによって寝ている間も心拍数が高止まりしやすくなります。
睡眠不足・身体的疲労の蓄積
慢性的な睡眠不足や過労状態も、夜間の心拍数を高める大きな要因です。本来、十分な睡眠で副交感神経が優位になると心拍や血圧は安定するのですが、睡眠が不足したり疲労が溜まった状態が続くと、身体は日中と同じようにストレスを感じてしまいます。
その結果、休んでいるはずの夜間にも交感神経が過剰に働き、熟睡していても脈が速い状態(動悸)を引き起こしやすくなります。
「なかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚める」「休んでも疲れが取れない」といった状態が続く方は、要注意です。また、オーバートレーニング(過度な運動負荷)も身体に慢性疲労とストレスを与え、安静時心拍数の増加を招きます。
就寝前の刺激物の影響
寝る前の行動や摂取物も、睡眠中の心拍に影響を与えます。
カフェイン
カフェインは代表的な交感神経刺激物質で、夕方以降にコーヒーやエナジードリンクを摂ると入眠を妨げるだけでなく、夜間も心拍数が高めに推移しがちです。カフェインの効果は摂取後数時間持続するため、夜遅くの摂取は避けるべきです。
アルコール
お酒は一時的には入眠を促すように感じますが、体内でアルコールが分解される過程で交感神経が刺激されるため、睡眠後半に心拍数が上昇して睡眠を浅くしてしまいます。深酒すると夜中に動悸がしたり汗をかいて目覚めることがあります。
喫煙
ニコチンも強い覚醒作用と血管収縮作用があり、心拍数を増加させます。就寝前の一服はリラックスどころか心臓に負担をかけてしまうので避けましょう。
寝室環境の問題
眠る環境が悪いと、体が十分に休まらず心拍数が下がりにくくなります。
室温
特に室温や湿度の影響は大きく、暑すぎる寝室では寝苦しさから交感神経が働いて心拍数が上昇します。汗をかいて脱水気味になると心拍も増えるため、夏の夜はエアコン等で適度に涼しく保つことが重要です。
逆に冬場は冷えすぎると体が震えて代謝が上がるため、適切な暖房で快適な温度を維持しましょう。
騒音・照明
騒音や明るすぎる照明も睡眠を妨げ、ストレス反応で脈拍が上がる原因になります。寝室は静かで暗い環境に整え、快適な寝具で体をリラックスさせることが大切です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
いびきや無呼吸を伴う睡眠時無呼吸症候群がある人は、夜間に心拍数が異常に高くなるケースが知られています。
無呼吸発作によって血中酸素が不足すると、体は酸素を確保しようとして心臓を激しく動かし、まるで寝ている間にマラソンをしているかのような負荷がかかります。その結果、睡眠中にも心拍数が100を超えることも珍しくありません。
SASの人は睡眠中ずっと心臓がフル稼働状態になり、心臓を休める暇がなくなるため、高血圧や不整脈、心筋梗塞など心臓病のリスクも高まります。もしいびきが酷い、日中の強い眠気があるなどSASが疑われる場合は、早めに専門医に相談して治療することが重要です。
その他の疾患や要因
上記以外にも、心拍数が慢性的に高い背景としていくつかの医学的要因が考えられます。
例えば甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)では代謝が亢進して安静時でも頻脈になることがあります。また不整脈(心房細動など)が発生していると脈が急に速く乱れる場合があります。更年期の女性ではホルモンバランスの変化により動悸が起こりやすくなることも知られています。
これらは頻度としてはそれほど高くありませんが、「明らかにおかしいほど心拍数が高い状態」が繰り返し起こる場合には、念のため循環器内科などで検査を受け、潜在的な疾患がないか確認することをお勧めします。
睡眠中の心拍数が低いのは大丈夫?徐脈になるケース
次に、「睡眠時の心拍数が低すぎないか?」という心配について説明します。スマートウォッチのデータを見ると、深夜に自分の心拍数が40台や30台/分まで下がっていて驚いた、という声もよく聞きます。
結論から言えば、睡眠中に心拍数が非常に低くなること自体は珍しいことではなく、多くの場合は問題ありません。むしろ前述の通り、睡眠中は副交感神経が優位になって心拍がゆっくりになるのが正常な反応です。
生理的な徐脈は問題なし
特に若く健康な人やスポーツを習慣的に行っている人では、安静時や睡眠時の心拍数が一般平均より低めである傾向があり、それは心肺機能が高く効率の良い心臓である証とも言えます。
実際、循環器専門医の所見でも「就寝中に心拍数30台になる人も珍しくない。病気がなく症状もないなら問題ないケースが多い」という報告があります。
睡眠中は副交感神経の働きで一時的に房室ブロック(二度房室ブロック)など軽度の不整脈が出現し、心拍が間引かれることもありますが、これも多くの場合病的意義はありません。無症状の徐脈であれば基本的に緊急な対処は不要で、経過観察で良いことがほとんどです。
注意が必要な徐脈
しかし一方で、極端な徐脈には注意も必要です。一般的に安静時心拍数が40拍/分以下になるような高度の徐脈では、めまいや失神、倦怠感などの症状が現れることがあります。
起きて活動している時に脈拍があまりにも遅いと、全身に十分な血液を送れず脳貧血を起こす恐れがあります(立ちくらみや意識消失など)。睡眠中であっても、徐脈が重度になると夜間頻尿を引き起こしたり、浅い眠りになるといった指摘もあります。
ただし、そのレベルになると多くは心臓の伝導異常(洞不全症候群や高度房室ブロックなど)といった基礎疾患が関与しているケースです。健康な若い人で症状もないのに心拍数が40未満まで下がることは稀です。
医療機関への相談の目安
もしご自身の睡眠中の最低心拍数がしょっちゅう40を切るような場合には、一度医療機関で相談してみても良いでしょう。
特に日中にも脈が遅くて息切れしやすいとか、血圧が低くめまいがあるといった症状がある場合は要チェックです。医師による検査(ホルター心電図など)で徐脈の程度と原因を評価してもらい、必要ならペースメーカーなどの治療が検討されます。
ただし繰り返しになりますが、症状がなく元気に過ごせているなら、睡眠中の徐脈は過度に心配しすぎないことも大切です。むしろ「よく休めているサインかも」くらいに捉えて、日々の傾向を見守るのが良いでしょう。
睡眠時の心拍数を安定させる改善策とアドバイス
ここまでの内容から、睡眠中の心拍数が高すぎる場合も低すぎる場合も、それぞれ原因やポイントが見えてきました。最後に、睡眠時の心拍数を適正な範囲に保ち安定させるための具体的な対策をまとめます。
心拍数は自律神経の影響を大きく受けますので、生活習慣や睡眠環境を整えることが何より重要です。以下の改善策を実践することで、夜間の心拍数がより安定し、質の良い睡眠につながるでしょう。
規則正しい生活リズム
不規則な生活は自律神経を乱し、心拍数の安定を妨げます。毎日ほぼ一定の時刻に就寝・起床する習慣をつけましょう。
睡眠時間も不足しないよう確保します(成人では1日7時間前後が目安)。休日だからと昼まで寝たり、徹夜と寝だめを繰り返すような生活は避け、体内時計が整うよう心がけてください。
就寝前のリラックス
寝る前には副交感神経を優位にする工夫を取り入れましょう。
電子機器を控える
スマホやパソコンの画面から出る強い光は脳を刺激するため、就寝1時間前には電子機器の使用を控えるのがおすすめです。
リラックス法
代わりにストレッチや深呼吸、軽い読書など心身が落ち着く時間を過ごします。ベッドに入ってから「早く寝なきゃ」と焦ると余計に交感神経が働いてしまいます。
緊張を感じる方はゆっくりした腹式呼吸を試してみてください。息を吐くことに意識を置くと副交感神経が働き、心拍数が穏やかになります。
入浴
暖かい湯船に浸かるのも体温が下がる過程で眠気を誘い、リラックス効果があります。
カフェイン・アルコールを控える
前述したように、カフェインやアルコールは睡眠時の生理に悪影響を与えます。夕方以降のカフェイン摂取は避けるのが理想で、どうしても飲みたい場合はデカフェやカフェインレスのお茶に切り替えましょう。
アルコールも寝酒代わりにしないようにしましょう。適量を守っても就寝直前の飲酒は睡眠の質低下につながるため、飲むなら寝る3時間以上前までに切り上げます。
喫煙習慣のある方も、せめて寝る前の一服は我慢しましょう(ニコチンは交感神経を刺激し入眠を妨げます)。
適度な運動習慣
日中に適度に体を動かすことは、安静時心拍数を下げ夜間の心拍安定に寄与します。ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなど自分が続けやすい運動を週に数回取り入れてみましょう。
運動により心肺機能が高まると安静時の余裕が生まれ、夜間も心臓がゆっくり休めるようになります。
運動のタイミング
ただし注意点として、就寝直前の激しい運動は逆効果です。寝る直前にハードな筋トレやランニングをすると交感神経が興奮し、しばらく心拍数が高いままになって寝付きが悪くなります。
運動は遅くとも就寝の2時間前までに終えるようにし、夜遅く運動せざるを得ない日はストレッチ程度の軽いものに留めましょう。
寝室環境の改善
睡眠環境を整えることは、夜間の心拍数コントロールに直結します。
温度・湿度
前述の通り、室温は快適な範囲に保つことが大切です。暑い夏はエアコンや扇風機で適度に室温を下げ、寝汗で脱水しないようにしましょう。夏場に寝室が暑いと深部体温が下がらず、心拍数も高止まりしてしまいます。
反対に冬は寒すぎると交感神経が刺激されるため、暖房や湯たんぽ等で冷えすぎないようにします。
光と音
また、光と音のシャットアウトも重要です。就寝時は部屋をできるだけ暗くし、遮光カーテンやアイマスクを活用してください。耳障りな騒音がある場合は耳栓やホワイトノイズで対策しましょう。
必要であれば加湿器で適度な湿度(50%前後)を維持し、喉の乾燥や鼻づまりを防ぐことも安眠につながります。
寝具の見直し
体に合った寝具(マットレスや枕)を使うことも、睡眠中の心拍数を安定させる意外なポイントです。
寝具が硬すぎたり柔らかすぎたり、自分の体格に合わないと、寝姿勢が不自然になって体がリラックスできず、深い眠りを妨げてしまいます。反対に、質の良い寝具は体圧を適切に分散し、寝ている間の体への負担を減らしてくれます。
寝苦しさが解消されれば自然と副交感神経が働きやすくなり、心拍数も安定しやすくなるでしょう。
例えば、亀屋家具では米国ブランドのシモンズ(Simmons)や日本の老舗日本ベッドなど、高品質なマットレスを取り扱っています。これらのマットレスは寝心地が良く体をしっかり支えてくれるため、寝返りがスムーズになり睡眠の深さが向上すると言われます。
現在使っている寝具に違和感がある方は、この機会に自分に合った寝具への買い替えも検討してみてください。寝具環境を改善することも、結果的に夜間の心拍数を適正に保つ助けとなるでしょう。
専門医への相談も視野に
上記のような生活習慣の改善や環境調整を行ってもなお、「夜間の頻脈・徐脈が改善しない」「どうしても不安が拭えない」という場合は、無理せず専門家に相談しましょう。
不眠や睡眠時無呼吸症候群であれば睡眠外来や呼吸器内科、頻脈や徐脈の不安が強ければ循環器内科を受診すると良いでしょう。医師の診察によって、必要なら睡眠時の精密検査(ポリソムノグラフィー)や24時間心電図検査を行い、適切な治療法や対策を提示してくれます。
「何も異常ありません」と確認できれば安心できますし、万一問題が見つかっても早期対応できます。最近はスマートウォッチのデータを見せると診療の参考にしてくれる医師もいますので、気になる記録があれば保存して受診時に相談してみてください。
睡眠データとの付き合い方
最後に、睡眠データとの付き合い方について触れておきます。ウェアラブル端末で心拍や睡眠スコアを計測できるようになった反面、数値に神経質になりすぎることの弊害も指摘されています。
睡眠専門医も「数字にとらわれすぎるのは逆効果」と述べており、データはあくまで目安として活用し、多少心拍数が上下しても一喜一憂しないことが大切です。
大事なのは日中の体調やパフォーマンスであり、夜間に心拍数が十分下がっていなくても日中元気であれば過度な心配は不要です。逆に数字が良くても疲労感が強いなら生活を改善すべきでしょう。
要はバランスです。データは健康管理の参考程度に留め、自分の体感と照らし合わせながら、ゆったりとした気持ちで眠りにつくようにしてください。
まとめ:心拍数データと上手に付き合い、質の良い睡眠を
睡眠時の心拍数は、私たちの心身の状態を映し出す鏡です。高すぎる心拍も低すぎる心拍も、それぞれ原因を探って適切に対処することで、多くの場合は改善できます。
大切なのは、データに振り回されすぎず、リラックスして眠ることです。睡眠中に心拍数が下がるのは自然なことであり、それは身体がしっかり休めているサインでもあります。一方、夜間に心拍数が上がりがちな人も、原因となる生活習慣や環境を整えれば、次第に安定してくるでしょう。
普段から規則正しい生活とストレスコントロールを心がけ、必要に応じて専門家の力も借りながら、自分に合った快適な睡眠を追求してみてください。そうすれば、心拍数も穏やかに推移し、朝目覚めたときの爽快感や日中のパフォーマンス向上につながるはずです。
心地よい睡眠と安定した心拍リズムを手に入れて、毎日の健康管理に役立てていきましょう。あなたの眠りがより良いものとなるよう、今日からできることを少しずつ実践してみてください。おやすみ前のちょっとした工夫が、きっと大きな変化をもたらすはずです。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。