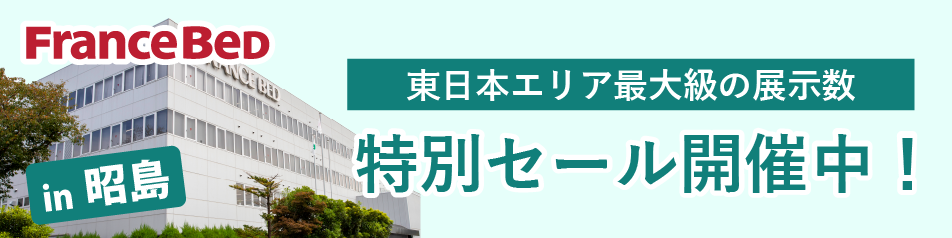.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
睡眠のゴールデンタイムの真実と質の良い睡眠を取る方法
公開日:2025.08.17(日)
「夜22時~深夜2時は睡眠の"ゴールデンタイム"」――この話を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
美容や健康のため「この時間帯に寝ないと成長ホルモンが出ない」「肌に悪い」といった話が広まり、多くの人が22時前後には寝なくては...とプレッシャーを感じてきました。
しかし実際の生活では、仕事や学業の関係で毎日22時に就寝するのは難しい人も多いものです。
本記事では、この"睡眠のゴールデンタイム"説の真偽を最新の研究や医学的見解から検証し、質の良い睡眠をとるための具体的な方法を解説します。「理想の時間に寝られないけど大丈夫?」「遅く寝てもちゃんと成長ホルモンは出るの?」といった疑問に答えながら、睡眠の質を高める生活習慣や寝室環境の工夫、さらに快眠を支えるマットレス選びのポイントまでお伝えします。
"睡眠のゴールデンタイム"説はどこから生まれたのか
まずは「睡眠にゴールデンタイムがある」という考え方がどこから来たのかを見てみましょう。
かつて日本では、「夜22時から深夜2時までの間に睡眠をとらないと成長ホルモンが十分に分泌されない」「美容と健康のためにはこの時間帯の睡眠が必要」という説が広く信じられてきました。この時間帯はいつしか"ゴールデンタイム"と呼ばれ、雑誌やテレビ、美容業界などを通じて常識のように語られていたのです。
なぜ22時~2時という具体的な時間がゴールデンタイムとされたのでしょうか?
これには日本人の昔の生活リズムが関係しています。当時は現在ほど夜更かしの習慣が一般的でなく、多くの人は夜10時~12時頃までには就寝していました。そのため睡眠の前半3~4時間で分泌される成長ホルモンがちょうど深夜2時前後にピークとなり、「夜22時~2時に寝れば成長ホルモンがしっかり出る=熟睡できる・美肌になれる」という考え方が生まれたと考えられます。
言い換えれば、この説は当時の平均的な就寝時間に基づいた説だったのです。
こうした"ゴールデンタイム"の考え方は長らく「睡眠の常識」として語り継がれてきました。特に美容分野では「お肌のゴールデンタイム」という言葉が定着し、「夜10時までに寝ないと肌に悪い」と半ば都市伝説のように広まっていたのです。
しかし近年、この古い常識に対して疑問を投げかける専門家が増えてきました。
現在の医学的見解:時間帯よりも深い睡眠が重要
結論から言えば、「22時~2時に眠らないと成長ホルモンが出ない」というのは間違いです。
現代の睡眠医学や生理学の研究によれば、成長ホルモンの分泌は特定の時刻ではなく、睡眠の深さとタイミングに大きく関わっています。
人間の睡眠は浅い「レム睡眠」と深い「ノンレム睡眠」が約90分周期で繰り返されます。入眠後しばらくして訪れる最初の深いノンレム睡眠(深睡眠)こそが成長ホルモン分泌のピークとなることが分かっています。このため、睡眠開始後3~4時間の深い睡眠が非常に重要なのです。
実際、成長ホルモンは入眠後最初のノンレム睡眠時に集中的に大量分泌されます。これは時間帯に関係なく起こる生理現象であり、極端に言えば何時に寝ても、寝入りばなの深い睡眠さえ確保できていれば成長ホルモンはしっかり分泌されるということです。
たとえ夜更けに就寝し朝遅めに起きたとしても、睡眠の前半で深い眠りがとれていれば成長ホルモン分泌は行われることが確認されています。重要なのは「いつ寝るか」という時計の時刻そのものではなく、「寝ついてからいかに深く眠れるか」なのです。
24時間を通した成長ホルモンの分泌
近年の研究では、成長ホルモンは睡眠中だけでなく24時間を通して分泌されており、仮に一晩徹夜したとしても通常睡眠中に出る分泌が日中にある程度補われることも報告されています。
もちろん夜間の深い睡眠中に分泌される量が一日で最大であることは事実ですが、必ずしも「決まった時刻に眠らなければならない」わけではないのです。
現在の標準的な見解では、「質の良い睡眠=深い睡眠をしっかり取ること」が大切であり、極端に早寝の時間帯そのものよりも睡眠の質と量に重きが置かれています。
このように、医学的には"睡眠のゴールデンタイム"説は否定されつつあります。それどころか、「22時を過ぎてしまった...」と不安になったり落胆したりすること自体がストレスとなり、かえって睡眠の質を下げてしまいかねません。
大切なのは就寝時刻よりも最初の深い眠り。このポイントを押さえていれば、多少寝る時間が前後しても必要なホルモン分泌や休息効果は得られるのです。
睡眠の質を高めるための具体的な方法
では、どうすれば「質の良い睡眠=深い睡眠」を得られるのか、具体的なポイントを見ていきましょう。
睡眠の質を左右する要因は大きく分けて(1)生活習慣、(2)環境要因、(3)心身のリラックス状態の3つがあります。
規則正しい生活リズムと適度な運動
日中の過ごし方が夜の睡眠に大きく影響します。
日中に適度に体を動かし、朝起きる時間と寝る時間を毎日なるべく一定に保つことが基本です。例えば軽いジョギングや早歩きといった有酸素運動を週に数回以上習慣づけると、寝つきが良くなり睡眠時間が延び、深い睡眠も増加するとの報告があります。
運動により日中に適度な疲労を溜めることで夜ぐっすり眠れるようになるわけです。
ただし注意点として、就寝直前の激しい運動はかえって脳を覚醒させ睡眠を妨げるため避けましょう。運動は遅くとも寝る2~4時間前までに済ませるのが望ましく、寝る直前はストレッチ程度の軽いもので十分です。
入浴で体温調節
寝る前の入浴(ぬるめのお湯でリラックス)も深い睡眠を促す効果があります。
40℃程度の湯船に10~15分浸かると深部体温(身体内部の温度)が上昇し、入浴後約1時間かけて平熱より0.5~1.0℃ほど下がっていきます。この体温の下降がスムーズな入眠と深いノンレム睡眠をもたらすことがわかっています。
したがって、就寝の1~2時間前までに入浴を済ませ、湯冷めして心地よく感じる頃に布団に入るのが理想です。就寝直前に熱い風呂に入るのは逆効果なので避けましょう。
入浴が難しい場合でも、足湯や蒸しタオルで体を温めるだけでも多少効果があります。
就寝前の光・音・デジタル機器の管理
人間の体内時計は光に強く影響されます。
夜間に明るい光、特にブルーライト(青白い光)を浴びると脳が「昼間だ」と錯覚してしまい、眠りを誘うホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されて入眠が遅くなります。
スマートフォンやPC、テレビなどの画面は就寝1時間前にはオフにし、部屋の照明も暖色系でやや落とした明るさ(一般的な室内なら豆電球程度)に調整しましょう。蛍光灯やLEDの白い光ではなく、オレンジ色の間接照明などに切り替えるだけでも効果があります。
また静かな環境も重要です。人は完全な静寂より多少の環境音があった方が安心する場合もありますが、テレビの音や会話、車の騒音など断続的な音は睡眠を妨げます。
エアコンの室外機や時計の音が気になる人は、耳栓やホワイトノイズ、ヒーリング音楽で音をかき消すと良いでしょう。
カフェイン・アルコール・食事の注意点
夕方以降のカフェイン摂取は避けましょう。
コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは摂取後数時間効果が持続し、脳を興奮状態に保ってしまいます。個人差はありますが、寝る6時間前以降はカフェインレスの飲み物に切り替えるのが無難です。
また寝酒代わりのアルコールも実は逆効果です。少量のアルコールは入眠を助けることもありますが、アルコールが分解される夜中に交感神経が刺激され眠りが浅く途切れやすくなります。
夕食は就寝の3時間前までに済ませ、就寝直前の満腹や空腹を避けるようにします。消化にエネルギーを取られると深い睡眠が阻害されるため、夜食は極力控えめにしましょう。
どうしてもお腹が空いて眠れない場合は消化の良い温かいミルクやスープ程度に留めるのが良策です。
ストレス対策とリラックス法
心身が緊張した状態ではなかなか寝付けません。
就寝前は心を落ち着ける時間を作りましょう。仕事や勉強で頭が冴えたまま布団に入るのではなく、寝る30分前からスマホやパソコンを閉じ、照明を落としてストレッチやヨガ、深呼吸をするなどリラックスタイムを設けます。
お気に入りのアロマオイルを焚いたり、穏やかな音楽を流したりするのも効果的です。ラベンダーの香りは鎮静効果が高いことで知られています。
また、翌日の心配事で頭がいっぱいだと眠れないものです。紙に気がかりを書き出して「明日対処しよう」と客観視する、軽い読書で気分をそらすなど、自分なりのストレス解消の工夫をしてみましょう。
就寝前のひとときは自分を労わり、緊張を解きほぐす時間とすることで、スムーズに眠りに入ることができます。
「ゴールデンタイムに寝られない」人への対処法
「仕事やシフトの関係でどうしても夜22時までに寝るなんて無理!」という方も多いでしょう。
では、理想とされる時間に眠れない人はどうすればよいのでしょうか? ここまで述べてきた通り、睡眠の質が大事とはいえ睡眠不足が慢性化すれば健康に悪影響が出るのも確かです。
生活リズムを可能な範囲で一定に保つ
たとえ就寝時刻が遅めでも、毎日バラバラの時間に寝起きするよりは生活リズムを一定に保つ方が体内時計への負担が少なくなります。
平日と休日で極端に寝る時間・起きる時間がずれると「社会的ジェットラグ」といって時差ボケのような状態を引き起こしてしまいます。
夜型の生活にならざるを得ない人は、自分の中で無理のない就寝時刻(例:午前1時など)を設定し、それをできるだけ毎日守るようにしましょう。起床時間も一定にし、朝起きたら日光を浴びて体内時計をリセットします。
毎朝同じ時間にカーテンを開けて朝日を浴びるだけでも、夜自然と眠くなるリズムが作られていきます。
短い昼寝や早寝で睡眠負債を解消
平日の睡眠時間がどうしても短い場合、「睡眠負債」を貯めすぎない工夫が必要です。
まとめて寝だめするのではなく、小刻みに不足分を補うのがポイントとされています。具体的には、日中に15~20分程度の仮眠(パワーナップ)をとったり、可能な日はいつもより1時間早く就寝するなどして少しずつ睡眠時間を追加します。
休日にまとめて長く寝るのは一見効率的に思えますが、朝遅くまで眠ると夜になっても眠気が来ず、生活リズムが乱れてしまいます。
どうしても週末に寝不足を解消したいときは、普段より2時間程度長く寝るまでに留め、昼近くまで寝過ごさないようにしましょう。起床後は必ず朝日を浴びて体内時計をリセットし、夜更かしの連鎖を防ぐことも大切です。
夜勤・シフトワーカーの場合
夜勤などで昼夜逆転の生活を送る方は、より一層の工夫が必要です。
勤務が終わって日中に眠る際は、遮光カーテンやアイマスクで夜のような暗さを確保し、耳栓や静かな音楽で周囲の生活音を遮断するよう努めましょう。昼間の睡眠でもできるだけ連続した深い睡眠をとることが重要です。
可能であれば、勤務前に1~2時間の仮眠をとる、勤務明けの朝日はサングラスで浴びる光量を減らすなど、体内リズムへの刺激を調整します。
プレッシャーを手放し、前向きに考える
「早く寝なきゃ」と焦るほど目が冴えてしまう――これは多くの人が経験するところです。
ゴールデンタイム説に振り回されて「もう◯時だからダメだ...」と自分を追い込んでしまうのは逆効果です。むしろ「遅い時間に寝ても、深く眠れれば大丈夫」と発想を転換しましょう。
実際、夜型の人でも途中で起きず深い眠りがとれていれば成長ホルモンは分泌されます。ですから「睡眠の質を上げればカバーできる」と前向きに考え、生活習慣改善や環境調整に注力することが大切です。
必要以上に焦らず、「起きてしまったら無理に寝ようとせず一旦リラックスしてから再度眠気を待つ」くらいの心持ちでいましょう。睡眠への過剰な不安や思い込みを手放すことも、結果的に快眠への近道なのです。
快眠のための寝室環境とマットレスの工夫
質の良い睡眠を得るには、生活習慣だけでなく寝室環境や寝具にも目を向けることが大切です。人間は環境によって眠りの深さが左右されます。
寝室の光環境
寝室はできるだけ暗くすることが基本です。街灯や朝日が差し込んで明るい場合は遮光カーテンを利用し、電子機器の小さなランプ類もテープで隠すなどして光源を遮断しましょう。
完全な真っ暗闇が怖いという人は、足元だけをほのかに照らすフットライトなど、直接目に入らない微かな照明を置くと安心です。就寝中に光を感じると脳が刺激を受け眠りが浅くなるため、タイマーで夜間は消灯するのも手です。
朝は自然光でスッキリ目覚められるように、遮光カーテンでも薄手のものを使い、起床時刻に合わせてカーテンが自動で開く装置などを利用するのも良いでしょう。
寝室の音環境
寝室は静かなほどよいですが、無音だとかえって気になる人もいます。
基本はエアコンや家電の音、外部の騒音をできるだけ低減することです。エアコンの室外機音が響くなら防振ゴムを敷く、時計はコチコチ音のしない静音タイプに替える、窓には厚手のカーテンや二重窓シートを導入するなど、できる範囲で防音対策をしましょう。
それでも難しい場合は、ヒーリングミュージックや耳栓で対処します。ゆったりとした音楽や自然音は副交感神経を優位にし、眠気を誘う効果もあります。
一方、テレビをつけっぱなしで寝落ちするのはNGです。映像や音の刺激で睡眠が浅くなりやすいため、眠くなったらタイマーオフを活用するなど習慣づけましょう。
温度・湿度と寝具の素材
寝室の温度管理も快眠には重要です。暑すぎず寒すぎず、快適に感じる温度帯を保ちましょう。
一般的に寝室の適温は夏は約25〜27℃程度、冬は13〜21℃程度と言われます。湿度は50〜60%が目安です。
夏場はエアコンを上手に使い、タイマーや弱風設定で一晩通して25〜27℃前後をキープすると良いでしょう。冬場は暖房で空気を暖めすぎると乾燥しますので、加湿器で湿度を調整しつつ足元を湯たんぽなどで温めるのがおすすめです。
寝具についても季節に応じた工夫を。通気性の良い素材(綿やリネン、通気性ウレタンなど)は夏の寝苦しさを軽減し、保温性の高い素材(羽毛布団や毛布、フランネルシーツなど)は冬の冷えから守ってくれます。
枕・マットレスの選び方
自分の体に合った寝具選びは快眠の要です。特にマットレスは「寝心地の主役」とも呼ばれ、体をしっかり支える役割があります。
マットレス選びで重視したいポイントは、体圧分散・寝姿勢サポート・通気性の3つです。
まず体圧分散とは、体が接する面で重みを均等に受け止めることで、肩や腰など一部に負担が集中しないようにする性質です。体圧分散性の高いマットレスは寝返りも打ちやすく、血行を妨げにくいため、朝起きたときの体の痛みやこわばりを軽減します。
次に寝姿勢のサポート。人間の背骨はS字カーブを描いていますが、寝ている間もその自然なカーブを保てることが理想です。マットレスが柔らかすぎると沈み込み、硬すぎると体が浮いてしまい、どちらも背骨に負担がかかります。
良いマットレスは程良い反発力で身体を面で支え、腰や背中が沈み込みすぎないよう支えてくれます。特に腰痛持ちの方はこの点が重要です。
最後に通気性。睡眠中、人はコップ一杯分以上の汗をかくと言われます。マットレス内部に湿気がこもるとカビやダニの原因にもなり不衛生です。通気性に優れた構造や素材(スプリング構造や通気口付きのマットレス、通気性繊維のクッション材など)は、一晩中爽やかな寝心地を保つのに役立ちます。
マットレスや枕は実際に試してみないと自分に合うか分からない部分もあります。専門店で横になって試すのがベストですが、難しい場合は信頼できるメーカーの評判や保証内容(体験期間・交換制度など)も参考にしましょう。
亀屋家具で取り扱う主要マットレスブランドの特徴
最後に、快眠の要となるマットレスについて、亀屋家具で取り扱いのある代表的なマットレスブランドをご紹介します。
日本ベッド、シモンズ、サータ、フランスベッドといった国内外の有名ブランドの特徴を見てみましょう。それぞれ体圧分散性・通気性・サポート力に工夫を凝らした製品を展開しており、自分に合ったマットレス選びの参考になります。
日本ベッド(Japan Bed)
日本ベッドは1926年創業の国産マットレスメーカーのパイオニアで、老舗ならではの品質の高さで知られています。一流ホテルにも多数採用されており、「日本人の好みや気候を知るメーカー」として上質な寝心地を追求しています。
日本ベッドのマットレス最大の特徴は、独自開発のポケットコイルスプリングを高密度に配列している点です。ポケットコイルとはコイルバネ一つひとつが独立して布に包まれたスプリングで、荷重に応じて個別に沈み込むため体圧分散性に優れます。
日本ベッドはこのポケットコイルを高密度に並べ、体をしっかり面で支える構造にしているので、肩や腰が沈み込みすぎず理想的な寝姿勢を保ちやすいのです。柔らかさと支え感のバランスが良く、「雲の上に寝ているようだけど芯がある」と評される寝心地です。
また、日本の気候を踏まえた通気設計や耐久性の高さにも定評があります。長く使えてヘタリにくいため、一度購入すると10年以上愛用している方も多いブランドです。
シモンズ(Simmons)
シモンズはアメリカ発祥で150年以上の歴史を持つ世界的ベッドメーカーです。ホテル業界でも「世界のベッド」と称され、世界中の高級ホテルでシモンズのベッドが採用されています。
シモンズといえばポケットコイルマットレスの元祖ともいえる存在で、シモンズ独自技術で作られた高品質なポケットコイルを用いたマットレスが看板商品です。
シモンズのポケットコイルマットレスは、一つひとつのコイルが独立して身体を点で支えるため、体のラインに沿って沈み込み体圧を均等に受け止める構造になっています。これにより肩や腰への負担を軽減し、自然な寝姿勢を保つサポート力を発揮します。
またポケットコイルは振動が伝わりにくい利点もあり、同じベッドで寝ている相手の寝返りの揺れが気になりにくいというメリットもあります。
シモンズはこの技術をいち早く確立し世界に広めたブランドであり、その快適さから「一度シモンズを使うと他に戻れない」というファンも多いほどです。通気性もコイル構造ゆえに確保されており、蒸れにくく清潔に保ちやすい点も魅力です。
サータ(Serta)
サータはアメリカ国内で長年売上No.1を誇るトップクラスの寝具ブランドで、高級ホテルへの採用実績も豊富な世界的メーカーです。日本で販売されているサータのマットレスはすべて国内生産されており、日本人の体格や嗜好に合わせた調整がされています。
サータのマットレスの特徴は、最高グレードのポケットコイルを使用し、高い体圧分散性と耐久性を実現している点です。
特に有名なのが「ポスチャーシリーズ」というやや硬めのマットレスで、しっかりとした寝心地が特徴です。硬めと言っても表面の詰め物で程よいクッション性があり、身体の沈み込みを抑えつつも圧力を分散する絶妙なバランスを実現しています。
体格の良い人でも深く沈み込みすぎず安心して眠れる硬さで、「腰痛が軽減した」「朝スッキリ起きられるようになった」といった声も多く聞かれます。またサータは耐久性にも定評があり、コイルのへたりにくさや表面素材の丈夫さで長期間性能を維持します。
さらに振動の少なさもポケットコイルならではで、同じくポケットコイルのシモンズと並び振動伝達の少ない静かな寝心地です。総じてサータは「硬めでしっかり支える寝心地」を求める方や、「ホテルのような上質な眠り」を家庭で味わいたい方に選ばれているブランドです。
フランスベッド(France Bed)
フランスベッドは国内シェアNo.1を誇る日本の老舗ベッドメーカーで、高齢者向け介護ベッドから一般家庭用まで幅広く展開しています。
フランスベッドのポリシーは「清潔で長持ちする寝具」であり、「きれいがつづく」高衛生マットレスというキャッチコピーでも知られます。具体的には、防ダニ・抗菌防臭加工や通気構造の工夫で、マットレスを長期間清潔に保てる点が強みです。
肝心の寝心地に関しては、フランスベッドは独自の高密度連続スプリングを採用しています。これは一本の鋼線からできたコイルを連続的に編み込んだスプリングで、面で身体を支える構造が特徴です。
体圧を面で受け止めるため背中や腰が局所的に沈まず、理想的な寝姿勢を維持しやすいという利点があります。連続スプリングは耐久性が高く、ヘタリにくいのもメリットです。
さらにフランスベッドは通気性にも配慮した製品が多く、例えば高機能クッション材「ブレスエアーⓇ」を使ったシリーズでは、寝返りのたびに内部に空気が循環する構造で蒸れを防ぎ快適さを保ちます。
また衛生面では、丸ごと水洗いできるマットレスや、防菌・防臭素材を使ったマットレスカバーなども開発されています。「清潔・安心・快適」を重視する方にとってフランスベッドは有力な選択肢でしょう。
なお、フランスベッドは国内生産ゆえのきめ細かな品質管理とアフターサービスの良さでも評価されています。長期間使うマットレスだからこそ、国産ブランドの信頼感を重視する方にも支持されています。
以上、主要ブランド4社の特色を見てきました。それぞれ快眠のための工夫(体圧分散、通気性、サポート力などを凝らしており、自分の好みや体格に合ったものを選ぶことが大切です。
亀屋家具では日本ベッド、シモンズ、サータ、フランスベッドの正規商品を取り扱っており、実際に試しながら比較検討することも可能です。ぜひ専門スタッフに相談しつつ、自分にフィットする一品を見つけてください。
まとめ
従来言われてきた"ゴールデンタイム"にとらわれすぎず、最新の科学的根拠に基づいて自分にできる睡眠改善策を取り入れてみてください。
重要なのは就寝時刻よりも睡眠の質(深い睡眠)です。成長ホルモンは入眠後最初の3時間程度の深いノンレム睡眠で集中的に分泌され、これは就寝時刻に関わらず起こる現象です。
生活習慣の見直し(規則正しいリズム、適度な運動、入浴、光・音の管理、ストレス対策)と寝室環境の整備(適切な温度・湿度、暗さ・静かさ、質の良い寝具)により、質の高い睡眠を得ることができます。
また、どうしても理想の時間に眠れない場合でも、生活リズムを一定に保ち、睡眠負債をこまめに解消することで健康への影響を最小限に抑えることができます。
十分な睡眠は美容と健康の基礎です。日々の積み重ねで睡眠の質を高め、翌朝すっきりと目覚められる生活を目指していきましょう。質の良い眠りが毎日の活力と笑顔につながることを願っています。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。