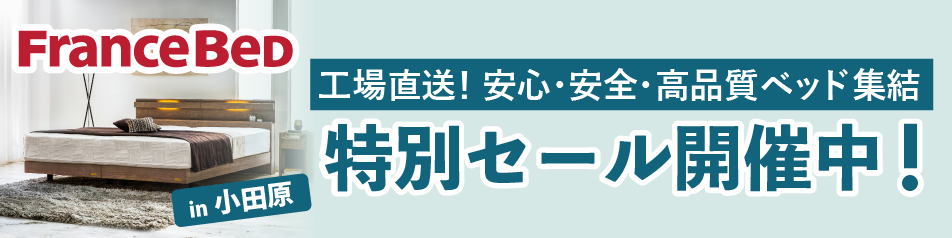.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
マットレスのずれ防止:100均グッズで簡単DIY
公開日:2025.05.14(Wed)
マットレスが寝返りのたびにズレてイライラすることはありませんか?特にパイプベッドやフローリングに直接マットレスを敷いていると、ツルツル滑って毎朝直すのは大変です。実はこのマットレスのずれ、100円ショップのグッズを使った工夫で簡単に防止できます。この記事では、お金をかけずにできるマットレスずれ防止の方法を、滑り止めアイテムの効果や選び方、設置方法と共に紹介します。マットレスのズレを解消して、快適な睡眠環境を手に入れましょう!
マットレスがずれる主な原因と放置するリスク
ずれる主な原因
マットレス自体が軽い:薄いウレタンマットレスなどは厚みのあるスプリングマットレスより軽く、寝返りの力で動きやすくなります。体格の良い人ほど寝返り時の力が強く、軽いマットレスや敷きパッドがズレやすい傾向があります。
カバーやシーツの生地が滑りやすい:シルクやサテン生地のカバーは肌触りが良い反面、摩擦が少なくマットレスがずれやすくなります。サラサラした素材だと滑ってしまうため、タオル地など摩擦の高いシーツに変えるだけでも改善することがあります。
ベッドの構造・配置:マットレスを置く土台(床板)が平らで囲いがないタイプだと横方向に動きやすいです。また、マットレスとベッドが壁に近すぎると、寝ている間に無意識に壁を蹴ってずらしてしまう可能性もあります。壁にぴったり付ければ動かないように思えますが、ベッドは壁から少なくとも5cmは離すのが良いでしょう(通気性確保のためにも大切です)。
放置するとどうなるか
マットレスの位置ズレを放っておくと、寝姿勢が崩れて体に余計な負担がかかったり、隙間に子どもが落ちそうになったりと危険です。小さなズレでも気になって睡眠の質を下げてしまうので、早めに対策しておくのが良いでしょう。では次に、お金をかけずにできる具体的なずれ防止策を見ていきましょう。
100均グッズで解決!マットレスずれ防止策あれこれ
滑り止めシートを敷いて摩擦力アップ
マットレス下に敷くシートでズレを抑える基本対策です。100均やニトリで手軽に入手でき、四隅や中央に敷くだけで効果を発揮します。薄手タイプからクッションタイプまで種類も豊富です。
「マット専用すべり止めシート」などの100均グッズを敷くだけ!最もお手軽なのは、マットレスと土台の間に滑り止めシートを敷く方法です。100均でも写真のようなマット用滑り止めシート(10cm角×4枚入りなど)が販売されており、これをマットレス下に挟むだけでOK。「貼るだけ簡単ズレ防止」とパッケージにある通り、四隅にペタッと置くだけで摩擦が増えてかなり動きにくくなります。
使い方のコツは、小さくカットして複数枚を配置することです。一枚ものの大判シートを使う場合でも、10cm四方くらいに切ったものを四隅+中央付近に満遍なく敷くと効果的です。こうすることで部分的に強い摩擦力が働き、よりずれにくくなるのです。
ただし注意点もあります。100均の滑り止めシートは種類豊富で安いですが、厚みや材質が薄手のものだと大きなマットレスには力不足な場合もあります。クッション性のある厚手タイプや粘着シートタイプを選ぶと良いでしょう。もし100均シートで効果が弱い場合は、ニトリなどで売られている大判サイズのずれ防止シートを検討してください。ニトリの滑り止めシート(NT3など)はラグ用ですが他社製と同じくらい効果があり、大きめサイズでマットレスにも使いやすいと評判です。価格はサイズによりますが1,000円前後(130×185cmで約800円)なので、それでも十分お手頃です。
豆知識:除湿シートで滑り止め代用?
ベッドとマットレスの間に敷く「除湿シート」(湿気取りシート)は、実は少しの滑り止め効果も期待できます。製品によっては裏面が滑り止め加工されているものもあり、カビ対策とずれ防止の一石二鳥です。ただし完全に滑らないわけではないので、あくまで補助的に考えましょう。
ズレ防止テープ・耐震マットで貼り付け固定
滑り止めシート以外にも、貼るタイプのずれ防止グッズが役立ちます。例えば100均の「クッション滑り止めシート(シール式)」は、マットの四隅に直接貼って使う小さな滑り止めパッドです。10cm角ほどのシールをマットレスの裏面に貼り付けるだけで、かなり動きにくくなります。クッション素材で厚みがあるため、踏んでも違和感が少ないメリットがあります。
他にも、家具の耐震マット(ジェルシート)を代用する方法もあります。透明な四角いジェル状の耐震マットは、もともと家具の下に敷いて地震時の滑りを防ぐものですが、粘着性が高く滑り止めとして優秀です。1枚あたり15kg程度の重さに耐えられる製品が多く、四隅に貼ればほとんどのシングルマットレスは支えられるでしょう。何度も貼り直しできるタイプなら位置調整も気軽にできます。
粘着テープ類を使う際の注意点は、貼る場所の材質確認です。マットレス側が布生地の場合、強力すぎるテープだと生地を傷めたり、逆に弱すぎてすぐ剥がれたりします。床板側が無垢木材だとテープ跡が残る恐れもあります。心配なときは布ガムテープなどで一度保護し、その上から滑り止めテープを貼ると安心です。また、定期的に剥がして湿気を飛ばすなどお手入れも心掛けましょう。
結束バンド+ブックエンドでDIY固定ストッパー
「結束バンド」と「ブックエンド」でマットレスずれをしっかり止める!DIY好きの方には、このユニークな方法が人気です。用意するのは100均で買える穴あきの金属製ブックエンド(仕切り板)と結束バンド(インシュロック)だけ。ブックエンドをベッドフレームの縁にあてがい、フレームの隙間や網棚に結束バンドで括り付ければ、即席のストッパーが完成します。ちょうどブックエンドの垂直の板部分がマットレスの側面を支える形になり、以降マットレスが横方向へズレるのをしっかり食い止めてくれます。
この方法は特に**パイプベッド(スチールメッシュの床板)**で効果的です。実際に試した方も「とても簡単でしっかり止まる!」とその効果に驚いています。筆者の知人も二段ベッドのマットレスずれに悩んでいましたが、同様に四隅にブックエンドを結束バンド留めしたところぴったり動かなくなりました。まさに目からウロコのアイデアですね。
ポイント:結束バンド留めのコツ
複数ヶ所を固定する:ブックエンド1枚につき結束バンドを2~3本通し、しっかり締め付けます。余裕があればブックエンド自体も前後2枚使い、合計4枚でマットレスの四隅を囲むと完璧です。
耐久性に注意:結束バンドは時間が経つと劣化して切れることもあります。長期間使う場合はときどき緩みや破損がないか点検し、必要に応じて新品に交換しましょう。紫外線に強い屋外用バンドを使うと劣化しにくいです。
なお、ブックエンド以外にもL字金具や木板などで代用する方法もありますが、100均のブックエンドは安く加工不要なため手軽です。見た目は多少目立ちますが、マットレス下に隠れる部分も多いので気にならない方にはおすすめの裏技と言えます。
100均「万能ベルト」でマットレスをバンド固定
マットレスが大きく動く場合や、二つのマットレスを並べて使っている場合には、ベルトでまとめて固定してしまう方法もあります。市販のマットレスバンド(連結バンド)は2000円前後しますが、ダイソーの「万能ベルト」(全長約245cm)なら110円で入手可能。これを使えば安く同じような効果が期待できます。
実際の使い方は簡単で、マットレスをぐるっと一周巻いてバックルで締めるだけ。例えばシングルマットレス2台を横並びにしているご家庭では、写真のように中央部分をベルトでまとめて固定すると隙間が生じにくくなります。
黒いベルトでしっかりと二枚のマットレスが連結され、寝返りを打っても真ん中にズレが生じません。実際にこちらを使用した方も「3ヶ月経って一度もズレなし、快適」と太鼓判を押しています。
一方、シングルマットレス1枚がベッドフレーム上でずれる場合にも、このベルト固定は有効です。フレームごと巻くようにベルトを回せばマットレスと土台を一体化できます。ただしベッドの形状によってはベルトがずり落ちてしまうので、フレームの凹凸や脚部で引っ掛けるように通すと安定します。どうしても難しい場合は無理に巻かず、前述の滑り止めシート等と組み合わせて補助的に使うとよいでしょう。
豆知識:市販マットレスバンドとの違い
専用のマットレスバンド製品は幅広(5cm以上)でより頑丈な作りになっています。値段は高めですが、その分締め付け力も強く緩みにくいです。例えば楽天で人気の「お留めさん」は超大型のスーツケースベルトのような製品で、キングサイズベッド(幅約225cm)でも余裕をもって巻ける長さがあります。100均ベルトは幅2cm程度とやや細いので、心配な方は2本使いして幅を補ったり、思い切って専用品を検討するのもアリです。
その他:カバー類の工夫やベッド自体で対策
上記以外にも、細かな工夫でマットレスの滑りを軽減できる場合があります。
ボックスシーツで包み込む:マットレスとベッドマット(敷きパッド)を一体化させる裏技です。大きめのボックスシーツでマットレスごと土台を包むようにすると、シーツがずれ止めの役割を果たします。完全に固定はできませんが、多少の動きなら抑えられるでしょう。
シーツクリップ・バンドを活用:敷きパッドやベッドシーツ用のクリップ留めバンド(四隅に付けるゴムやワンタッチクリップ)も100均で入手できます。元々寝具ずれ防止用ですが、シーツとマットレスをしっかり固定することで間接的にマットレスのズレも軽減します。特にマットレスと一緒にシーツまで滑って困る場合に有効です。
ベッドの脚に滑り止めを敷く:ベッド自体がフローリング上で動いてしまう場合は、脚の下に小さく切った滑り止めマットを挟みましょう。これで床との摩擦が増し、ベッドの位置ズレを防止できます(床の傷防止にも◎)。脚のないフラットベッドの場合も、四隅に滑り止めシートを噛ませておくと安心です。
また、根本的な対策としてベッドフレーム選びも見直してみましょう。フレームにマットレスを沈み込ませる「落とし込み構造」のベッドなら、物理的に囲われるためマットレスがずれにくくなります。一方、フレームよりマットレスが上に突き出るようなタイプ(上乗せ式)は動きやすい傾向があります。もし買い替えを検討するなら、囲い付きのフレームや滑り止めボード付きの商品を選ぶと良いでしょう。
専用グッズやブランド製品との比較もチェック
100均DIYでかなりの効果が期待できますが、市販の専用グッズや有名ブランド製品にはどのようなものがあるかも知っておきましょう。長所と短所を比較して、自分に合った方法を選ぶ参考にしてください。
ニトリや無印良品の滑り止めシート:手頃な価格で大判サイズが手に入ります。例えばニトリの「すべり止めシート」は185×185cmで約1,000円と大きく、切って使えるのでマットレス全面に敷くことも可能。100均の小さいシートを何枚も組み合わせるより一枚で済む分、設置も楽です。無印良品から直接の滑り止めマットは出ていませんが、同等品をホームセンター等で購入できます。広範囲に敷ける分、効果も安定して高いでしょう。
マットレスバンド・連結ベルト:二台のマットレスの隙間対策には専用品が安心です。無印良品でも脚付きマットレス用の連結ベルトを販売しており、シングル2台を固定してキングサイズ化する用途などに使われます。市販のマットレスバンド(例えば幅5cm×長さ10m程度の連結ベルト)なら、ダブルベッドにも対応可能です。価格は2千円前後と高めですが、「ずれが完全になくなった」「締め付けても緩まない」と満足度も高いようです。100均ベルトで物足りなさを感じたら、専用品への切り替えを検討しても良いでしょう。
ずれ防止クリップ・ストッパー:シーツや敷きパッド用のクリップ以外にも、マットレスと床板を挟んで固定する専用クリップが市販されています。こちらはベッドフレームの縁に工具で取り付け、物理的にマットレスの動きをせき止めるものです。DIYのブックエンド法を簡易キット化したような商品で、ネジ締めする分頑丈ですが、取り付けに手間がかかり見た目も多少目立ちます。100均DIYで代用できる範囲なので、よほど頻繁にズレて困る場合以外は優先度低めです。
高級ブランドの工夫:一流マットレスブランド(シモンズ、フランスベッド等)の製品では、マットレス生地や構造自体がずれにくい工夫を凝らしているものもあります。例えばマットレス裏面に滑り止め加工を施したモデルや、重量がありびくともしない分厚いマットレスも存在します。厚みがあり重量級のマットレスほど動きにくいのは確かで、実際に厚さ30cm超のシモンズのマットレスに替えたら一切ズレなくなったという声も聞きます(その代わり価格も相応ですが…)。現在お使いのマットレスが極端に軽いようであれば、いずれ買い替えを検討するのも根本解決策と言えるでしょう。
最後に、筆者おすすめの組み合わせをご紹介します。「滑り止めシート+結束バンド固定」の組み合わせです。まずマットレス下に薄手の滑り止めシートを敷き、基本的なずれを防止。その上で、どうしても動いてしまう方向にのみ結束バンドやベルトで固定具を追加します。こうすれば普段はシートだけで十分で、子どもが飛び跳ねる時だけストッパーが効く、といった万全の状態になります。「パイプベッドで子どもが大暴れだからシートだけでは無理だったけど、バンドも付けたら完璧になった!」というケースもありますので、複数アイテム併用もぜひ試してみてください。
まとめ:100均DIYでマットレスのずれを卒業しよう!
毎朝ズレたマットレスを直すストレスから解放されると考えると嬉しいですよね。幸い、マットレスのずれ防止はちょっとした工夫と安いグッズで十分実現可能です。滑り止めシートで「滑らない土台」を作り、必要に応じてバンドやクリップで「動かない固定」を施せば、あの厄介なズレともお別れです。
何より100均アイテム中心で揃うので、お財布にも優しく気軽に試せます。まずは手近なダイソーやセリアで滑り止めグッズをチェックしてみましょう。実際に対策してみると、あんなに悩んでいたのが嘘のようにマットレスがピタッと止まりますよ。ぜひ今回紹介した方法を参考に、あなたのベッド環境に合ったずれ防止策を実践してみてください。快適な睡眠と目覚めの良い朝を、低予算DIYで手に入れましょう!
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。